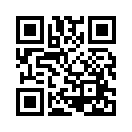2018年06月12日
素人考え
今、6月12日午後2時半、ワールドカップ開幕を直前に控えた最後のテストマッチ、パラグアイ戦の当日(シンガポールでは世紀の会談の真っ最中)に書いている。
前の試合、スイス戦の後、あるスポーツ新聞のインターネットの記事には次のようにある。
『就任から2戦2敗となった西野朗監督(63)はそれでも前向きだった。選手たちのプレーが求める水準に達しているのか?と聞かれると「非常にいいと思います。選手たちのコンディションは躍動感がありますし、連動して攻守に高い水準のパフォーマンス。グループとしてのパフォーマンスが若干取れていない。フィニッシュのところの課題は残しましたけど、守備から攻撃のスイッチ、攻撃から守備の連動性は、求めているところまできている」と評価した。W杯まで時間がなく、残る国際親善試合は12日パラグアイ戦(インスブルック)の1試合だけ。危機感は? と問われると「毎試合、毎試合選手とトライして、チーム、私自身もマイナスのイメージはまったくもっていませんし、いいチャレンジをしていると思います。チャレンジしていく、前向きにとらえられる状況。チームとして危機感というところは、まったく感じてはいません」と断言した。』
小学校の体育の授業でサッカーを始めて以来50年近くになるので、私自身はサッカーの素人とは違うと自負してきた部分があったが、あのスイス戦を終えての私の感想と日本代表チームの監督の認識の間にこれほどの差があるとは、私は自分の長年の経験から来る自分の見立ての確信が大きな音を立てて崩れていく喪失感を禁じ得ない。私が培ってきたサッカー観は何だったのかと。
1点目の失点シーン。大迫(選手名敬称略)が負傷のため交代した直後だった。私が長年監督を務めてきた底辺レベルの高校生チームでは、「集中しろ!」と大声で指示する場面だなと思って見ていた。右サイドバックの酒井が、俊足の相手選手にチャレンジして突破された。カバーすべき吉田との距離があんなにある状況でなぜ飛び込まなければいけなかったのか、レベルの低いC級コーチである私にはまったく理解できなかった。何回あのシーンを見直しても、ドイツでプレーしているトップ・レベルの選手が何を考えていたのか、今もってわからない。PKを与えた吉田のプレーが云々されているが、私には、酒井のチャレンジしようとする判断と、酒井と吉田の連携が問題だとしか思えない。
“神は細部に宿る。”本番直前にしての連携不足、このワン・プレーが現在のチーム状況を象徴しているのではないか。しかし、上記記事に曰く“連動して攻守に高い水準のパフォーマンス。…攻撃から守備の連動性は、求めているところまできている。”
2点目の失点シーン。攻撃のCKの時、私が監督をしていた底辺レベルのチームでは、二人CBが相手ゴール前に上がる時には、必ずカウンターを受けないように、プレーを切って終われと毎回大声を出していた。そして、CKからボールがサイドに流れていって、相手チームのボールになろうかという時に、吉田、槙野の二人のCBが相手ゴール・エリア付近で歩いている。さすが日本代表ともなると、味方がボールを奪い返して、もう一度クロスが来るのを待つということなのかなと思っていたら、そこからボールをつながれて、CBが二人とも戻り切れないうちに失点してしまった。
ワールドカップ本番では、対戦する3チームはいずれもFIFAランクが日本より上。安定した守備から攻撃をするのではなかったのか。そんな記事をどこかで読んだ気もしていたのだか、私の勘違いか。そして、上記記事に曰く、西野監督は“チームとして危機感というところは、まったく感じてはいません。”
底辺コーチの私は、危機感しか持つことができないでいる。50年にわたる経験から養われた私のサッカー観は、どこでどう間違ったのか。どうすれば、あの試合の中に西野監督と同じ光景を見ることができるのか、次のC級コーチ・リフレッシュ研修の時に、誰か教えてほしいと痛切に思う。
今夜のパラグアイ戦が終わった後、その結果にかかわらず、私は西野監督にこう言ってもらいたい。「本番を見ていてほしい。テストマッチの出来不出来は大きな問題ではない。私は突然解任された前監督の後を引き継いだ。前監督の無念を思う時、私は可能性を高めただけでは許されないことは十分に分かっている。本番の結果を見ていてほしい。それがすべてである。もし、結果が伴わなかったとき、私は会長とともに責任を取って、サッカー界から足を洗う。」
そして、本番が終わった後晴れ晴れとした表情で、私にも「そんな見方しかできないから、底辺レベルのコーチのままなんだよ。」と、言い放ってもらいたい。そうしたら、私は「本当にごめんなさい。」心の底から謝ります。
Posted by Okuno at
15:37
│Comments(0)
2018年06月08日
大きく育っていく源
バレンシアアカデミー和歌山校が開校して早くも二か月が過ぎました。アカデミー生と保護者の皆さんの日々のご理解とご協力に感謝しています。
開校二か月を経過した今、ここまでを振り返り、これからの方向を少し考えてみました。
私たちが開校に当たって、基本方針としたところは、次の点です。
①どこまでも広くて、深くて、高いサッカーの世界を子どもたちに伝えたい。
②その具体的なイメージとして参考にすべきモデルを、“スペイン・サッカー”とする。
③そんな“世界”を夢に見て、夢の先へ飛び出していこうとする積極的な意欲を持ち、課題に自分から進んで取り組んでいく子どもを育てたい。
④このことは、単にサッカーだけでなく、アカデミー生が人として成長していく過程でもプラスの影響を与えることが出来るはずである。
⑤そのために、ピッチの上のトレーニングだけでなく、情報の提供を含めたパッケージとしてアカデミーを運営していく。
⑥トレーニング・メニューは、サッカーの本質に立脚した内容にする。
◇目指すゴールがある。
◇攻守の切り替えの連続がある。
◇厳しいボールの奪い合いがある。
◇プレーヤーの瞬時の判断が必要である。
⑦トレーニングでは、次の点を重視する。
◇集中の維持が必要な、適度な強度を持った内容にする。
◇順番を待つだけの時間が存在しないメニューをできるだけ多くする。
◇プレーヤーが自ら力を出し切ろうとするように、コーチが声掛けする。
⑧情報提供の一つとして「Vamos a aprender」というアカデミー・ノートを配布していく。
さて、振り返りです。
アカデミー生は、熱心に全力でトレーニングに取り組んでくれています。より成果を高めていくために、要求していきたいのは次の点です。
①アカデミーで取り組んでいることをもっとしっかりと意識して、自分のチームでのトレーニングや試合の時に発揮してもらいたい。具体的には、
◇アカデミーで取り組んでいるターンを使おうとしていますか?
◇アカデミーで要求されているように、激しく厳しくボールを奪いにいっていますか?
◇ゲーム形式の練習や試合の時、ポジションの取り方(右・左・中)をしっかりと意識していますか?
②「Vamos a aprender」に時間をかけて取り組んでいますか。
「これやって提出せんとあかんの?」というアカデミー生がいますが、これは“宿題”ではありません。子どもたちは、学校や習い事で、常に“やらなくてはいけない”ことを押し付けられる状況に置かれています。もちろん、“やらなくてはいけない”ことが必要なこともありますが、子どもの成長にとって気を付けなくてはいけないのは、“やらなくてはいけない”と言われたことだけしていればよい、“やらなくてはいけない”と言われたこと以外はしなくても良いというように、心に刻み付けられていってしまうことです。
コーチが「アカデミー・ノートは、宿題ではないよ」と言うと、「やってきて出さなくても良いのなら、やらないでおこう」と“無意識に”判断してしまう心配はないでしょうか?
保護者の皆さんの中には「学校の宿題と同じだよ、やらなくてはいけないよ」というようなことになっていませんか?
アカデミー・ノートは何なのでしょう? 世の中には、“やらなくてはいけない”こと以外にどんなことがあるのでしょう?
子どもさんと一緒に考えてみてもらえればうれしいです。
開校二か月を経過した今、ここまでを振り返り、これからの方向を少し考えてみました。
私たちが開校に当たって、基本方針としたところは、次の点です。
①どこまでも広くて、深くて、高いサッカーの世界を子どもたちに伝えたい。
②その具体的なイメージとして参考にすべきモデルを、“スペイン・サッカー”とする。
③そんな“世界”を夢に見て、夢の先へ飛び出していこうとする積極的な意欲を持ち、課題に自分から進んで取り組んでいく子どもを育てたい。
④このことは、単にサッカーだけでなく、アカデミー生が人として成長していく過程でもプラスの影響を与えることが出来るはずである。
⑤そのために、ピッチの上のトレーニングだけでなく、情報の提供を含めたパッケージとしてアカデミーを運営していく。
⑥トレーニング・メニューは、サッカーの本質に立脚した内容にする。
◇目指すゴールがある。
◇攻守の切り替えの連続がある。
◇厳しいボールの奪い合いがある。
◇プレーヤーの瞬時の判断が必要である。
⑦トレーニングでは、次の点を重視する。
◇集中の維持が必要な、適度な強度を持った内容にする。
◇順番を待つだけの時間が存在しないメニューをできるだけ多くする。
◇プレーヤーが自ら力を出し切ろうとするように、コーチが声掛けする。
⑧情報提供の一つとして「Vamos a aprender」というアカデミー・ノートを配布していく。
さて、振り返りです。
アカデミー生は、熱心に全力でトレーニングに取り組んでくれています。より成果を高めていくために、要求していきたいのは次の点です。
①アカデミーで取り組んでいることをもっとしっかりと意識して、自分のチームでのトレーニングや試合の時に発揮してもらいたい。具体的には、
◇アカデミーで取り組んでいるターンを使おうとしていますか?
◇アカデミーで要求されているように、激しく厳しくボールを奪いにいっていますか?
◇ゲーム形式の練習や試合の時、ポジションの取り方(右・左・中)をしっかりと意識していますか?
②「Vamos a aprender」に時間をかけて取り組んでいますか。
「これやって提出せんとあかんの?」というアカデミー生がいますが、これは“宿題”ではありません。子どもたちは、学校や習い事で、常に“やらなくてはいけない”ことを押し付けられる状況に置かれています。もちろん、“やらなくてはいけない”ことが必要なこともありますが、子どもの成長にとって気を付けなくてはいけないのは、“やらなくてはいけない”と言われたことだけしていればよい、“やらなくてはいけない”と言われたこと以外はしなくても良いというように、心に刻み付けられていってしまうことです。
コーチが「アカデミー・ノートは、宿題ではないよ」と言うと、「やってきて出さなくても良いのなら、やらないでおこう」と“無意識に”判断してしまう心配はないでしょうか?
保護者の皆さんの中には「学校の宿題と同じだよ、やらなくてはいけないよ」というようなことになっていませんか?
アカデミー・ノートは何なのでしょう? 世の中には、“やらなくてはいけない”こと以外にどんなことがあるのでしょう?
子どもさんと一緒に考えてみてもらえればうれしいです。
Posted by Okuno at
09:32
│Comments(0)
2018年05月31日
私に夢を!
「私たちには経験値がある。」と、ある選手が試合後に話したと今朝の新聞に載っていた。寂しい話だ。私には、「私たちには経験値しかない。新しいものは何一つない。」という選手の悲痛な声のようにしか記事を読めなかった。
このブログは、ワールドカップ・メンバーを発表する前に書いている。ガーナ戦を終えて、今、私はロシアの大地でサッカーを愛する国民の大声援を大きなエネルギーに変えて、堂々と戦っている我が代表チームの雄姿を想像できないでいる。
日々進歩し続けるサッカー界では、前回のワールドカップ代表チームに、何か新しいものを付け加えないままに勝ち進むことは考えられない。前回大会でチームの中心であった選手たちにこの四年間でどんな力が加わったのか。テレビを通じて観戦した限りでは、私には何も感じられなかった。チームとして、どんな新しい武器が備わったのか、どんな新戦力が威力を発揮したのか、私にはトップを務めることの多い大迫の他、見て取れなかった。どんな新しい戦術なり考え方なりで世界のサッカーに新風を湧き上がらせようとしているのか、全く見て取ることができなかった。総じて言えば、私はロシアの大地に夢を見ることができないでいる。
西野監督は、私たちにどんな夢を見せようとしているのかが全く想像できないのだ。最低限のノルマをなんとかクリアしようとだけしている“中間管理職”のイメージが浮かんでくるだけだ。新しいものに挑戦する時間がないというのなら、なぜそんなタイミングで監督を交代させたのか。
私は、前監督が表明していた“デュアル”の結果を見届けたかった。日本サッカー界にとって新しいものだったからだ。上手くいかなくっても、その失敗を次のチャレンジに生かせば進歩につながる可能性があったからだ。思えば、外国人の代表監督にはいつも何か新しいものがあった。当たり前のことだが、新しいことへのチャレンジが成功を保証しているわけではない。彼らのチャレンジは、ビジネスとして自分の評価を上げようとする動機があったのかもしれない。しかし、それは少なくとも夢をもたらしてくれていた。世界のトップと戦うためには、その時点の日本代表チームには目に見えては顕在していない新しい武器を付け加えることが絶対必要だという意思を感じることができた。一方、日本人監督は、今ある戦力で最大限の成果を残すためにはどうすべきかという思考を感じてしまう。そこには、私は夢を見ることはできない。
サッカーの喜びって何だろう、スポーツの素晴らしさって何だろう、という本質を忘れてしまってはいけない。私は、“夢を見ること”だと思う。新しいことにチャレンジする夢、新記録を出す夢、新記録を見る夢、選手がシンクロして瞬間見せてくれる驚異的なパフォーマンスに立ち会うこと、スポーツはそんな夢を与えてくれるからこそ、夢の実現よりはるかに数多い失敗や挫折や敗北にも耐えられるのだと思う。スポーツの価値は、巷間よく言われるような、その“教育的”な側面にあるのでは決してないと私は考えている。人間にとって、もっと本質的な、原初的な感覚にこそスポーツの喜びはあると思う。少なくともノルマの達成にスポーツの喜びはないことだけは確信できる。
監督の交代劇の時、日本サッカー協会会長は、1%でも勝つ可能性を高めるためということを話していたと思う。私は、監督を交代させるほうが、国民にもっと夢を見てもらえる、もっとスポーツの喜びを感じてもらえるサッカーができると判断したと言ってもらいたかった。
ところで、勝つ可能性を高めるために監督を交代させたのなら、当然勝てなかったら責任を取って会長を自らクビにするのでしょうね。それがフェアな態度ですよね。それとも、可能性と言ったので、結果とは言っていないとか、監督をまた交代させて、日本サッカーを進歩させるのが私の責任だなどと、どこかの首相や大臣みたいなこと言わないですよね、スポーツマンなのだから。
さて、日本代表のメンバー発表だが、西野監督、あらためて私たちに夢を見させてくれる選考をしてください。前回大会より“個の力”を増幅させていない選手の選考は最小限にして、新しい可能性があるかもしれない選手を多く選考してください。そして、今、世界には存在しない“西野メソッド”を大舞台で試してください。、そのほうが、少なくとも私は、2022年の夢を見させてもらえるのですが。経験値が大事なら、新しい選手たちにロシアで経験値を積むチャンスを与えてください。そう、心から願っています。
最後に弁明しておきます。一つは、ガーナ戦後の大きな落胆のなかで慌てて書いたので文章の推敲が全然できていません。乱文をお詫びします。もう一つは、このブログは私の全く個人的な感想です。当クラブの公式見解ではありませんので、その点ご了承ください。
このブログは、ワールドカップ・メンバーを発表する前に書いている。ガーナ戦を終えて、今、私はロシアの大地でサッカーを愛する国民の大声援を大きなエネルギーに変えて、堂々と戦っている我が代表チームの雄姿を想像できないでいる。
日々進歩し続けるサッカー界では、前回のワールドカップ代表チームに、何か新しいものを付け加えないままに勝ち進むことは考えられない。前回大会でチームの中心であった選手たちにこの四年間でどんな力が加わったのか。テレビを通じて観戦した限りでは、私には何も感じられなかった。チームとして、どんな新しい武器が備わったのか、どんな新戦力が威力を発揮したのか、私にはトップを務めることの多い大迫の他、見て取れなかった。どんな新しい戦術なり考え方なりで世界のサッカーに新風を湧き上がらせようとしているのか、全く見て取ることができなかった。総じて言えば、私はロシアの大地に夢を見ることができないでいる。
西野監督は、私たちにどんな夢を見せようとしているのかが全く想像できないのだ。最低限のノルマをなんとかクリアしようとだけしている“中間管理職”のイメージが浮かんでくるだけだ。新しいものに挑戦する時間がないというのなら、なぜそんなタイミングで監督を交代させたのか。
私は、前監督が表明していた“デュアル”の結果を見届けたかった。日本サッカー界にとって新しいものだったからだ。上手くいかなくっても、その失敗を次のチャレンジに生かせば進歩につながる可能性があったからだ。思えば、外国人の代表監督にはいつも何か新しいものがあった。当たり前のことだが、新しいことへのチャレンジが成功を保証しているわけではない。彼らのチャレンジは、ビジネスとして自分の評価を上げようとする動機があったのかもしれない。しかし、それは少なくとも夢をもたらしてくれていた。世界のトップと戦うためには、その時点の日本代表チームには目に見えては顕在していない新しい武器を付け加えることが絶対必要だという意思を感じることができた。一方、日本人監督は、今ある戦力で最大限の成果を残すためにはどうすべきかという思考を感じてしまう。そこには、私は夢を見ることはできない。
サッカーの喜びって何だろう、スポーツの素晴らしさって何だろう、という本質を忘れてしまってはいけない。私は、“夢を見ること”だと思う。新しいことにチャレンジする夢、新記録を出す夢、新記録を見る夢、選手がシンクロして瞬間見せてくれる驚異的なパフォーマンスに立ち会うこと、スポーツはそんな夢を与えてくれるからこそ、夢の実現よりはるかに数多い失敗や挫折や敗北にも耐えられるのだと思う。スポーツの価値は、巷間よく言われるような、その“教育的”な側面にあるのでは決してないと私は考えている。人間にとって、もっと本質的な、原初的な感覚にこそスポーツの喜びはあると思う。少なくともノルマの達成にスポーツの喜びはないことだけは確信できる。
監督の交代劇の時、日本サッカー協会会長は、1%でも勝つ可能性を高めるためということを話していたと思う。私は、監督を交代させるほうが、国民にもっと夢を見てもらえる、もっとスポーツの喜びを感じてもらえるサッカーができると判断したと言ってもらいたかった。
ところで、勝つ可能性を高めるために監督を交代させたのなら、当然勝てなかったら責任を取って会長を自らクビにするのでしょうね。それがフェアな態度ですよね。それとも、可能性と言ったので、結果とは言っていないとか、監督をまた交代させて、日本サッカーを進歩させるのが私の責任だなどと、どこかの首相や大臣みたいなこと言わないですよね、スポーツマンなのだから。
さて、日本代表のメンバー発表だが、西野監督、あらためて私たちに夢を見させてくれる選考をしてください。前回大会より“個の力”を増幅させていない選手の選考は最小限にして、新しい可能性があるかもしれない選手を多く選考してください。そして、今、世界には存在しない“西野メソッド”を大舞台で試してください。、そのほうが、少なくとも私は、2022年の夢を見させてもらえるのですが。経験値が大事なら、新しい選手たちにロシアで経験値を積むチャンスを与えてください。そう、心から願っています。
最後に弁明しておきます。一つは、ガーナ戦後の大きな落胆のなかで慌てて書いたので文章の推敲が全然できていません。乱文をお詫びします。もう一つは、このブログは私の全く個人的な感想です。当クラブの公式見解ではありませんので、その点ご了承ください。
Posted by Okuno at
08:44
│Comments(0)
2018年05月28日
白と赤
まさに“衝撃的”としか言いようのないゴール・シーンばかりであった。ジダン監督は、就任から3年連続のヨーロッパ・チャンピオン。凄すぎる。有料放送を観る経済的余裕がないため、C・ロナウドのプレーをテレビで観ることはほとんどありませんが、この日観た彼のプレーは、ユニフォームの下に隠されているのは、本当に生身の人間であるのか疑問に感じてしまうような、金属的な機械的な動きであった。思い浮かんだのは、そう“エイトマン”。知っている人は少ないでしょうね。一度“エイトマン”の映像を探して観てください。きっと同感してもらえると思います。
あの日、私は、午前4時半くらいには起きて、後半からでも観戦しようと考えていました。齢を取ってくると朝が早いので、目覚まし時計に頼らなくても起きられると思っていたのでした。ところが、普段よりも眠りが深かったのか、妻に起こされてテレビをつけたら、何とすでに後半のアディショナル・タイムに入っていました。画面では、白と赤のユニフォームが対戦していました。すぐに白がレアル・マドリッドで、赤がリバプールと分かりました。
そして、そのユニフォームの色は、単に両チームを識別するだけのものではないということも、サッカー関係者なら誰でも理解できます。ユニフォームは、特にその色は、そのクラブの歴史であり、全サポーターのエネルギーを一つにまとめる旗印であり、クラブのアイデンティティの象徴そのものであるのです。だから、どのクラブもホーム・ゲームでは、基本的にはその色のユニフォームを着るのです。そして、ユニフォームのデザインの細部は変遷していっても、ベースになっている色を変えることはないのです。それは、許されないことなのだろうと思います。
では、あるクラブのユニフォームの色が、なぜその色になったのでしょうか。分かりませんね。分からないけど、どのクラブもその誕生は、少数の同好者でスタートしたのではないでしょうか。その時、たまたま何かの事情で、ある色になってしまった。そして、クラブがだんだんと成長するにつれて、その色に何らかの意味が付与されていった。そんなクラブが多いのではないでしょうか。いろいろな“神話”は後から付け加えられていった、そんなケースが結構あるのではないかと推測します。
我が海南フットボール・クラブのユニフォームの青黒の縦縞も、そんなケースの一つです。クラブが創設された頃は、他チームとの識別の意味合いが強く、時々色が変わっていったと記憶しています。現行の縦縞になったのは、ちゃんとしたクラブを目指すのなら、ユニフォームの色を固定しなくてはいけないということになり、それではどんな色にしようかと話し合いました。しかし、当然それぞれに好みがあり、そんなに簡単にまとまるはずがありません。そのうち何かの拍子に、その時とても強かったインテルみたいにしようと言い出す奴がいて、何となくそうなってしまったというのが、私の記憶です。だから、現在のユニフォームの色にもともと特別な意味が込められていたわけではありません。
しかし、一度固定されてしまったら、時間が経つにつれて、そのユニフォームにクラブの歴史が自然と織り込まれていって、クラブのアイデンティティを象徴するものに育ってきたのです。今や県内では、青黒の縦縞を見たら誰でも海南FCとその成績や雰囲気を思い浮かべてくれるのではないでしょうか。好き嫌いや好みの問題では、すでになくなっているのです。今更、色を変更することはできないのです。もし変更するとすれば、それは、まもなく創設50年を迎えようとするクラブの歴史と、現在のクラブのアイデンティティそのものを否定することにしかならないからです。時間が積み重なって、過去から現在に続く会員のサッカーを楽しんできた歴史が、すでに神聖なものとして青黒の縦縞のユニフォームに染みこんでしまっているのです。
だから、クラブの一員であるなら、できるだけ試合では青黒の縦縞を着なくてはいけないのです。ユニフォームに袖を通すということは、いわば自分のクラブへの帰属意識とプライドの表明であり、クラブに対する信仰心と忠誠心の発露でもあるのです。それは、どのクラブでも同じです。だから、試合は現在のチームの対戦でありながら、同時にユニフォームに染みこんでいるクラブの神話を背負った神聖な戦いにもなるのです。
今年のヨーロッパ・チャンピオンズリーグ決勝戦もまた、白と赤の神聖な戦いであり、あの試合は新たな神話の一部になっていくのでしょう。
あの日、私は、午前4時半くらいには起きて、後半からでも観戦しようと考えていました。齢を取ってくると朝が早いので、目覚まし時計に頼らなくても起きられると思っていたのでした。ところが、普段よりも眠りが深かったのか、妻に起こされてテレビをつけたら、何とすでに後半のアディショナル・タイムに入っていました。画面では、白と赤のユニフォームが対戦していました。すぐに白がレアル・マドリッドで、赤がリバプールと分かりました。
そして、そのユニフォームの色は、単に両チームを識別するだけのものではないということも、サッカー関係者なら誰でも理解できます。ユニフォームは、特にその色は、そのクラブの歴史であり、全サポーターのエネルギーを一つにまとめる旗印であり、クラブのアイデンティティの象徴そのものであるのです。だから、どのクラブもホーム・ゲームでは、基本的にはその色のユニフォームを着るのです。そして、ユニフォームのデザインの細部は変遷していっても、ベースになっている色を変えることはないのです。それは、許されないことなのだろうと思います。
では、あるクラブのユニフォームの色が、なぜその色になったのでしょうか。分かりませんね。分からないけど、どのクラブもその誕生は、少数の同好者でスタートしたのではないでしょうか。その時、たまたま何かの事情で、ある色になってしまった。そして、クラブがだんだんと成長するにつれて、その色に何らかの意味が付与されていった。そんなクラブが多いのではないでしょうか。いろいろな“神話”は後から付け加えられていった、そんなケースが結構あるのではないかと推測します。
我が海南フットボール・クラブのユニフォームの青黒の縦縞も、そんなケースの一つです。クラブが創設された頃は、他チームとの識別の意味合いが強く、時々色が変わっていったと記憶しています。現行の縦縞になったのは、ちゃんとしたクラブを目指すのなら、ユニフォームの色を固定しなくてはいけないということになり、それではどんな色にしようかと話し合いました。しかし、当然それぞれに好みがあり、そんなに簡単にまとまるはずがありません。そのうち何かの拍子に、その時とても強かったインテルみたいにしようと言い出す奴がいて、何となくそうなってしまったというのが、私の記憶です。だから、現在のユニフォームの色にもともと特別な意味が込められていたわけではありません。
しかし、一度固定されてしまったら、時間が経つにつれて、そのユニフォームにクラブの歴史が自然と織り込まれていって、クラブのアイデンティティを象徴するものに育ってきたのです。今や県内では、青黒の縦縞を見たら誰でも海南FCとその成績や雰囲気を思い浮かべてくれるのではないでしょうか。好き嫌いや好みの問題では、すでになくなっているのです。今更、色を変更することはできないのです。もし変更するとすれば、それは、まもなく創設50年を迎えようとするクラブの歴史と、現在のクラブのアイデンティティそのものを否定することにしかならないからです。時間が積み重なって、過去から現在に続く会員のサッカーを楽しんできた歴史が、すでに神聖なものとして青黒の縦縞のユニフォームに染みこんでしまっているのです。
だから、クラブの一員であるなら、できるだけ試合では青黒の縦縞を着なくてはいけないのです。ユニフォームに袖を通すということは、いわば自分のクラブへの帰属意識とプライドの表明であり、クラブに対する信仰心と忠誠心の発露でもあるのです。それは、どのクラブでも同じです。だから、試合は現在のチームの対戦でありながら、同時にユニフォームに染みこんでいるクラブの神話を背負った神聖な戦いにもなるのです。
今年のヨーロッパ・チャンピオンズリーグ決勝戦もまた、白と赤の神聖な戦いであり、あの試合は新たな神話の一部になっていくのでしょう。
Posted by Okuno at
21:32
│Comments(0)
2018年05月20日
デザイン
今年の「きのくに海南歩っとウォーク」に参加してくれたソラティオーラの会員は、大会の冊子に氏名が記載されたのが162人と、団体参加の中では最多であった。こんなに多くの会員が参加してくれたのか思うと、本当にうれしくなる。今年は、各カテゴリーの日程の都合で全員初日の19日(土)の参加となった。すると、距離によって出発時間は異なるものの、総合体育館の付近では青黒ストライプのプラクティス・シャツがやけに目立った。ここにもそこにもソラティオーラの会員がいるということが一目瞭然なのだ。なんか大会の主役になったようで、なんとなく誇らしくも思えてきた。
その総合体育館前のブースに、今年もシャウトがフランクフルトとスーパーボールすくいの模擬店を出してくれた。シャウト会員が多く参加してくれている。私ももちろんフランクフルトをいただいた。スーパーボールすくいをやる勇気はなかったし、誰も勧めてもくれなかったのはちょっと残念だった。
シャウトは、県内にママさんサッカーのチームや大会はあったが、一般女子のチームも大会もなかった1987年(今から30年前)に、中学生以上の女子なら誰でも入れる県内初のチームとして、その少し前まで私が勤めていた海南高校サッカー部の女子マネジャーを中心に結成したものだ。年月は流れたが、現在も県内には一般女子チームは一つだけだ。
そんなこともあって、和歌山国体が近づいてくる中で、シャウトが県女子選抜チームの候補選手のための強化指定クラブになった。補強選手も登録してくれたおかげでチーム力は格段に上がり、関西女子リーグの1部まで昇格できた。しかし、チーム関係者には強化指定を受ける時から大きな不安があった。それは、国体が終わった後、補強選手たちがどれだけシャウトに残ってくれるのだろうかという心配であった。国体後、その不安は当たってしまった。補強選手の中には、もっと上のレベルを目指す人もいたから、そのような思いを持っている人からすれば、練習回数も、サッカーにかける思いも、もともとシャウトに所属していた人とは違いがあって当然である。これは、どちらが良い悪いの問題ではもちろんない。シャウトに残ってくれた補強選手もいたが、大半はチームを離れていった。
国体前から予想していたことではあったが、シャウトの再建という、クラブにとっても、シャウトにとっても、国体強化以上の困難なミッションに取り組んでくれているのが、現在のスタッフとプレーヤーの皆さんなのである。
“誰でも参加できるクラブ”という、ソラティオーラの基本方針を受けて、シャウトを“デザイン”し直すことが必要であった。ソラティオーラという枠組みの中でのチームの位置づけ、現状での戦力とチームの目標、練習会の設定と練習参加の可能性、若い会員の募集、スタッフの人選と依頼、県女子サッカー界でのシャウトの役割、などなどの様々な要因が複雑に絡み合う中での、シャウトのこれからをしっかりと“デザイン”し、少しずつ着実に前に進みながら、時々は“デザイン”し直していくというたいへんな作業を担ってくれている。
シャウトにU-15クラスをスタートさせ、各地の中学生に声をかけて参加を募る。新たに火曜日に練習会を設定する。思った以上の会員が参加してくれているように思う。現時点では、今シーズン何とか関西女子リーグ2部を維持してもらいたいと願っている。
冒頭の「歩っとウォーク」でのシャウトの模擬店の話に戻るが、その取り組みもシャウト再発展のプロセスの一環としてのイベントであると私は理解している。模擬店ブースのテントには、スタッフとプレーヤーのほとばしる思いが熱いエネルギーとなって蓄積されつつあるように感じられた。
ソラティオーラ会員の皆さん、シャウトのチャレンジに力強いサポートをお願いします。
その総合体育館前のブースに、今年もシャウトがフランクフルトとスーパーボールすくいの模擬店を出してくれた。シャウト会員が多く参加してくれている。私ももちろんフランクフルトをいただいた。スーパーボールすくいをやる勇気はなかったし、誰も勧めてもくれなかったのはちょっと残念だった。
シャウトは、県内にママさんサッカーのチームや大会はあったが、一般女子のチームも大会もなかった1987年(今から30年前)に、中学生以上の女子なら誰でも入れる県内初のチームとして、その少し前まで私が勤めていた海南高校サッカー部の女子マネジャーを中心に結成したものだ。年月は流れたが、現在も県内には一般女子チームは一つだけだ。
そんなこともあって、和歌山国体が近づいてくる中で、シャウトが県女子選抜チームの候補選手のための強化指定クラブになった。補強選手も登録してくれたおかげでチーム力は格段に上がり、関西女子リーグの1部まで昇格できた。しかし、チーム関係者には強化指定を受ける時から大きな不安があった。それは、国体が終わった後、補強選手たちがどれだけシャウトに残ってくれるのだろうかという心配であった。国体後、その不安は当たってしまった。補強選手の中には、もっと上のレベルを目指す人もいたから、そのような思いを持っている人からすれば、練習回数も、サッカーにかける思いも、もともとシャウトに所属していた人とは違いがあって当然である。これは、どちらが良い悪いの問題ではもちろんない。シャウトに残ってくれた補強選手もいたが、大半はチームを離れていった。
国体前から予想していたことではあったが、シャウトの再建という、クラブにとっても、シャウトにとっても、国体強化以上の困難なミッションに取り組んでくれているのが、現在のスタッフとプレーヤーの皆さんなのである。
“誰でも参加できるクラブ”という、ソラティオーラの基本方針を受けて、シャウトを“デザイン”し直すことが必要であった。ソラティオーラという枠組みの中でのチームの位置づけ、現状での戦力とチームの目標、練習会の設定と練習参加の可能性、若い会員の募集、スタッフの人選と依頼、県女子サッカー界でのシャウトの役割、などなどの様々な要因が複雑に絡み合う中での、シャウトのこれからをしっかりと“デザイン”し、少しずつ着実に前に進みながら、時々は“デザイン”し直していくというたいへんな作業を担ってくれている。
シャウトにU-15クラスをスタートさせ、各地の中学生に声をかけて参加を募る。新たに火曜日に練習会を設定する。思った以上の会員が参加してくれているように思う。現時点では、今シーズン何とか関西女子リーグ2部を維持してもらいたいと願っている。
冒頭の「歩っとウォーク」でのシャウトの模擬店の話に戻るが、その取り組みもシャウト再発展のプロセスの一環としてのイベントであると私は理解している。模擬店ブースのテントには、スタッフとプレーヤーのほとばしる思いが熱いエネルギーとなって蓄積されつつあるように感じられた。
ソラティオーラ会員の皆さん、シャウトのチャレンジに力強いサポートをお願いします。
Posted by Okuno at
15:39
│Comments(0)