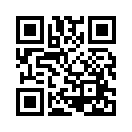2016年08月21日
リオ・オリンピック観戦記・最終回
リオ・オリンピックは、大成功の裡にフィナーレを迎えることになった。多分、ほとんどすべてのブラジル人にとって、今回のオリンピックはサッカー男子の初優勝がすべてであるだろう。
ブラジル、優勝おめでとう! 地球の反対側でのテレビ観戦でも、興奮が冷めやらないうちに、終わってみれば何とでも言えるといった程度の感想だが記しておきたい。
前半の終盤からテレビの前に座ったが、これがU-23の試合かと思ってしまう、素晴らしいゲームだった。延長戦を目前にして、リスクを取りにくい状況での両チームの阿吽の呼吸とでもいうようなゆったりとしたボール回しから、いったん縦パスが入ると、攻守ともに瞬間的に集中力が急上昇し、スピードアップする。その状況変化に誰もが反応する。
PKになって、ブラジルのゴール・キーパーは、キッカーがボールをセットしてスタンバイに入ってから、手に持ったタオルをゴール横に置きに行き、時間をかけてからスタンバイする。まるで宮本武蔵と佐々木小次郎の対決のように。しかし、5人目のキッカーに対してだけは、自分のほうが先にスタンバイした。ドイツの5人目のキッカーは、少し目に力が入っていないように感じられた。大会の得点王の一人になったが、決勝戦だけでは途中出場したものの、それほどの存在感が感じられなかった。
優勝を決めたネイマールのPK直後の涙の意味は何だったのだろうか。ブラジル人でも、飛び跳ねて喜ぶのではなく、泣くのだ。もちろん、全くの想像だが、あの涙は、「やっと解放された」という涙ではなかったのだろうか。成功すれば英雄、失敗すれば、PK戦は続くものの、もしその後の展開で負けるようなことになれば、地獄に落とされる。そんな状況からやっと解放されて流した涙。もし、失敗していれば、女子レスリングの吉田選手のように泣いただろうか。私には、ネイマールは泣くことさえ許されなかったと想像してしまう。そんな、物凄いシーンであった。
ブラジルのオーバーエイジ選手の選考と配置。自国開催とはいえ、日本の選考とは違いすぎる。4年後、日本は今回のブラジルのようなオーバーエイジ選考ができるだろうか。日本サッカー協会の幹部の力量はいかに。とは言え、それも含めて私たち日本サッカーの実力なのだ。オーバーエイジの一人、ボランチのレナトのディフェンス力、パス裁き、攻撃参加、どれをとっても素晴らしかった。(ただ、失点の場面ではドイツの選手のオーバーラップのカバーに入るため、マークしていた選手から離れたあと、その選手のカバーに味方選手が入ってこなかったため失点してしまったが)
ブラジルのオーバーエイジ選手であったボランチのレナトの素晴らしさはもちろんだが、そのこと以上にあのようなタイプのあのようなレベルの選手が次々と現れてくるブラジル・サッカーの力を感じてしまった。今の日本で、仮にレナトのレベルの選手が現れたとしても、特別な才能を持った特別な存在としかならないのではないだろうか。ブラジル・サッカーの質と量、歴史、文化にはただただ圧倒されてしまう。
完全アウェーのドイツもすごかった。流れの中でブラジルに得点させない集中力。パスワークで、ブラジルの守備を破る攻撃力。それを完全アウェーのマラカナンで表現できる力は、どこから湧いてくるのだろうか。得点シーンで、突然全力でオーバーラップを始めたドイツのサイドバックの選手は、そのスイッチをどうやって入れるのだろうか。あの大歓声の中では、誰かの指示でオーバーラップしたのではないだろう。まるで、100メートル走のピストルが鳴ったかのようなスタートであった。
イエロー・カードは何枚か出たが、汚いプレーの全くない、素晴らしいゲームであった。この試合を観ただけで、私の今日は終わってしまった。残りの時間は、その余韻に浸りながら過すことになるだろう。サッカーを好きになったおかげで、幸せになれた一日である。
ブラジル、優勝おめでとう! 地球の反対側でのテレビ観戦でも、興奮が冷めやらないうちに、終わってみれば何とでも言えるといった程度の感想だが記しておきたい。
前半の終盤からテレビの前に座ったが、これがU-23の試合かと思ってしまう、素晴らしいゲームだった。延長戦を目前にして、リスクを取りにくい状況での両チームの阿吽の呼吸とでもいうようなゆったりとしたボール回しから、いったん縦パスが入ると、攻守ともに瞬間的に集中力が急上昇し、スピードアップする。その状況変化に誰もが反応する。
PKになって、ブラジルのゴール・キーパーは、キッカーがボールをセットしてスタンバイに入ってから、手に持ったタオルをゴール横に置きに行き、時間をかけてからスタンバイする。まるで宮本武蔵と佐々木小次郎の対決のように。しかし、5人目のキッカーに対してだけは、自分のほうが先にスタンバイした。ドイツの5人目のキッカーは、少し目に力が入っていないように感じられた。大会の得点王の一人になったが、決勝戦だけでは途中出場したものの、それほどの存在感が感じられなかった。
優勝を決めたネイマールのPK直後の涙の意味は何だったのだろうか。ブラジル人でも、飛び跳ねて喜ぶのではなく、泣くのだ。もちろん、全くの想像だが、あの涙は、「やっと解放された」という涙ではなかったのだろうか。成功すれば英雄、失敗すれば、PK戦は続くものの、もしその後の展開で負けるようなことになれば、地獄に落とされる。そんな状況からやっと解放されて流した涙。もし、失敗していれば、女子レスリングの吉田選手のように泣いただろうか。私には、ネイマールは泣くことさえ許されなかったと想像してしまう。そんな、物凄いシーンであった。
ブラジルのオーバーエイジ選手の選考と配置。自国開催とはいえ、日本の選考とは違いすぎる。4年後、日本は今回のブラジルのようなオーバーエイジ選考ができるだろうか。日本サッカー協会の幹部の力量はいかに。とは言え、それも含めて私たち日本サッカーの実力なのだ。オーバーエイジの一人、ボランチのレナトのディフェンス力、パス裁き、攻撃参加、どれをとっても素晴らしかった。(ただ、失点の場面ではドイツの選手のオーバーラップのカバーに入るため、マークしていた選手から離れたあと、その選手のカバーに味方選手が入ってこなかったため失点してしまったが)
ブラジルのオーバーエイジ選手であったボランチのレナトの素晴らしさはもちろんだが、そのこと以上にあのようなタイプのあのようなレベルの選手が次々と現れてくるブラジル・サッカーの力を感じてしまった。今の日本で、仮にレナトのレベルの選手が現れたとしても、特別な才能を持った特別な存在としかならないのではないだろうか。ブラジル・サッカーの質と量、歴史、文化にはただただ圧倒されてしまう。
完全アウェーのドイツもすごかった。流れの中でブラジルに得点させない集中力。パスワークで、ブラジルの守備を破る攻撃力。それを完全アウェーのマラカナンで表現できる力は、どこから湧いてくるのだろうか。得点シーンで、突然全力でオーバーラップを始めたドイツのサイドバックの選手は、そのスイッチをどうやって入れるのだろうか。あの大歓声の中では、誰かの指示でオーバーラップしたのではないだろう。まるで、100メートル走のピストルが鳴ったかのようなスタートであった。
イエロー・カードは何枚か出たが、汚いプレーの全くない、素晴らしいゲームであった。この試合を観ただけで、私の今日は終わってしまった。残りの時間は、その余韻に浸りながら過すことになるだろう。サッカーを好きになったおかげで、幸せになれた一日である。
Posted by Okuno at
10:54
│Comments(0)
2016年08月15日
リオ・オリンピック 観戦記 その3
1次リーグの最終戦、スウェーデンには勝ったものの、決勝トーナメントには進めなかった。お盆の行事でざわざわしていたため、最終戦の感想を書くのが遅くなってしまったが、第2戦までの観戦記では中途半端に終わってしまうので、少し時間がかかってしまったが、最終戦を観て考えたことをまとめておこうと思う。
3試合を通じて素晴らしいと思ったのは、攻撃から守備への切り替えの早さである。ボールを失うと、前線からよくボールを追いかけていたと思う。さらに、そのことが体力的にきつい試合の終盤まで続けることができたことは、これからも日本サッカーのベースとして、どのレベルのサッカーでも取り入れていくべきスタイルだと思った。
残念なのは、終わってみれば、「あの1点、この1点」と振り返ってしまうことが現実になってしまったことだ。「あの失点がなかったら」、「このシーンでゴールが決まっていたら」、決勝トーナメントに進めたのに。ナイジェリア戦に引き分けていたら、コロンビア戦に勝っていたら…。「あの1点、この1点」を乗り越えるためには、何が必要だったのか。
試合後のインタビューで、日本チームのキャプテンが何度も「ちょっとした差」、「ちょっとした違い」を口にしていたように感じた。日本代表チームのキャプテンがなぜあのような発言をするのだろうか、不思議な気がした。その「ちょっとした差」こそが決定的な差であることは、日本代表チームのキャプテンともあろう選手には、わかっているはずなのに。その「ちょっとした違い」を乗り越えることが、どんなにたいへんなことかもわかっているはずなのに。
日本は、アジアではトップ・クラスのレベルまで到達することができた。それは、単に代表チームの強化で手に入れたポジションではなく、Jリーグの創設はじめ、底辺からの日本サッカー全体の取り組みの中で、やっと到達した場所であることは、サッカー関係者なら誰でもわかることだ。ということは、オリンピック・チームの「ちょっとした違い」は、代表チームの課題ではなく、日本サッカー全体の課題であることは明白だ。この「ちょっとした差」を乗り越えるために、日本中のサッカー関係者が膨大な努力を続けていくことが必要だ。
体操競技の内村選手が、団体戦の最終の鉄棒演技でものすごい演技をした。大会前から「団体で金メダル」を目標にしていて、あの演技である。テレビの解説者は、あの状況、あの場面で、あの演技ができるのは、これまで厳しい状況を何度も経験してきたからだ、というような意味のことを話していた。サッカーのオリンピック・チームは、なぜ「あの1点、この1点」の「ちょっとした差」を、体操の内村選手のように乗り越えられなかったのか。競技人口では、圧倒的に多いはずのサッカーが、体操競技の選手よりも真剣勝負の場が少ないのだろうか。サッカーのオリンピック代表選手たちは、厳しい状況を何度も経験しないままに、代表選手に選考され、オリンピックに臨んだのだろうか。
私がスペインのバレンシアに滞在したのはたった2週間であったが、その短い期間で感じたのは、底辺レベルからのサッカー・プレーヤーの密度の濃さであった。同じレベルのプレーヤー層の厚さ、その中からトップ・レベルに上がっていくには、単にサッカーの資質が優れているだけでは難しいだろうなあと想像させられるものであった。日本は、まだまだ、サッカーがうまいだけでトップ・レベルに上がっていける状況なのではあるまいか。
日本のサッカーが、世界との「ちょっとした違い」を乗り越えて、サッカーの一流国になっていくためには、バレンシアで感じた層の厚さを日本で実現していくよりほかに方法がないと考える。だから、私たちのような底辺レベルのサッカーが、もっともっと努力して層を厚くしていかなければならない。これが、今回のオリンピックでの日本代表チームの試合を観た私の総括です。みなさんはどんな感想を持ちましたか。
3試合を通じて素晴らしいと思ったのは、攻撃から守備への切り替えの早さである。ボールを失うと、前線からよくボールを追いかけていたと思う。さらに、そのことが体力的にきつい試合の終盤まで続けることができたことは、これからも日本サッカーのベースとして、どのレベルのサッカーでも取り入れていくべきスタイルだと思った。
残念なのは、終わってみれば、「あの1点、この1点」と振り返ってしまうことが現実になってしまったことだ。「あの失点がなかったら」、「このシーンでゴールが決まっていたら」、決勝トーナメントに進めたのに。ナイジェリア戦に引き分けていたら、コロンビア戦に勝っていたら…。「あの1点、この1点」を乗り越えるためには、何が必要だったのか。
試合後のインタビューで、日本チームのキャプテンが何度も「ちょっとした差」、「ちょっとした違い」を口にしていたように感じた。日本代表チームのキャプテンがなぜあのような発言をするのだろうか、不思議な気がした。その「ちょっとした差」こそが決定的な差であることは、日本代表チームのキャプテンともあろう選手には、わかっているはずなのに。その「ちょっとした違い」を乗り越えることが、どんなにたいへんなことかもわかっているはずなのに。
日本は、アジアではトップ・クラスのレベルまで到達することができた。それは、単に代表チームの強化で手に入れたポジションではなく、Jリーグの創設はじめ、底辺からの日本サッカー全体の取り組みの中で、やっと到達した場所であることは、サッカー関係者なら誰でもわかることだ。ということは、オリンピック・チームの「ちょっとした違い」は、代表チームの課題ではなく、日本サッカー全体の課題であることは明白だ。この「ちょっとした差」を乗り越えるために、日本中のサッカー関係者が膨大な努力を続けていくことが必要だ。
体操競技の内村選手が、団体戦の最終の鉄棒演技でものすごい演技をした。大会前から「団体で金メダル」を目標にしていて、あの演技である。テレビの解説者は、あの状況、あの場面で、あの演技ができるのは、これまで厳しい状況を何度も経験してきたからだ、というような意味のことを話していた。サッカーのオリンピック・チームは、なぜ「あの1点、この1点」の「ちょっとした差」を、体操の内村選手のように乗り越えられなかったのか。競技人口では、圧倒的に多いはずのサッカーが、体操競技の選手よりも真剣勝負の場が少ないのだろうか。サッカーのオリンピック代表選手たちは、厳しい状況を何度も経験しないままに、代表選手に選考され、オリンピックに臨んだのだろうか。
私がスペインのバレンシアに滞在したのはたった2週間であったが、その短い期間で感じたのは、底辺レベルからのサッカー・プレーヤーの密度の濃さであった。同じレベルのプレーヤー層の厚さ、その中からトップ・レベルに上がっていくには、単にサッカーの資質が優れているだけでは難しいだろうなあと想像させられるものであった。日本は、まだまだ、サッカーがうまいだけでトップ・レベルに上がっていける状況なのではあるまいか。
日本のサッカーが、世界との「ちょっとした違い」を乗り越えて、サッカーの一流国になっていくためには、バレンシアで感じた層の厚さを日本で実現していくよりほかに方法がないと考える。だから、私たちのような底辺レベルのサッカーが、もっともっと努力して層を厚くしていかなければならない。これが、今回のオリンピックでの日本代表チームの試合を観た私の総括です。みなさんはどんな感想を持ちましたか。
Posted by Okuno at
16:11
│Comments(0)
2016年08月08日
リオ・オリンピック コロンビア戦を観て
第2戦も勝てなかった。最終戦のスウェーデンに勝てば、決勝トーナメント進出の可能性も残されているが、前提になるのは、コロンビアがナイジェリアとの試合を引き分け以下の結果に終わることだ。
試合前、民放テレビでは、「ひどい試合で1-0で勝つよりは、美しい試合で2-3で負けるほうが良い」というような内容の、クライフの言葉を画面で流していた。ナイジェリア戦を1-0で勝つより、4-5で負けたほうが良いとでも言うかのように。これを見た瞬間、チャンネルをNHKのBS1に変えてしまった。クライフの言葉は、常に美しいサッカーで勝ち続けているチームが、たまに2-3で負けた時にだけ重みがある言葉だろうと私は思う。メダルに近づくためには初戦の勝利がなにより大切であると監督自身が話していた試合を、4-5で負けた試合の後で紹介する言葉では決してないと私は思う。
コロンビア戦、0-2とリードされた後、浅野のゴールで1-2とした時、NHKのアナウンサーは、「これが日本の底力だ!」と叫んだ。私は、その言葉は、3-2に逆点した時にいうことだろうと思ってしまった。なぜ、「1点では意味がない、早く次の1点を取れ、逆点して日本の底力を見せてくれ!」と叫ばないのだろうか。
試合の最終盤、南野の浮き球のパスを浅野が胸でコントロールし、シュートを打とうとしたところ、前に出てきたGKと接触してゴールがならなかったシーンで、解説者が南野のパスの素晴らしさと、浅野のコントロールの絶妙さを褒めていた。きれいなシーンには違いなかったが、試合当事国の放送としては、素晴らしいプレーを褒めるのではなく、それがゴールにつながらなかったことの残念さを、まずは口にしてほしかった。それが応援するということだろう。
この大会が、振り返ってみれば、“あの1点、この1点”ということにならなければよいのにと心から思う。スウェーデンに負けてしまえば、そんな言葉にさえならないのであるが、コロンビアがナイジェリアに引き分けたのに、日本がスウェーデンに引き分けてしまった場合など、「あのシーンのあの失点がなかったら」とか、「このシーンでシュートが決まっていたら」とかいう言葉が出てきてしまう結果にならなければよいのにと思う。
『過去の事実を変えることはできない。しかし、過去の事実の意味を変えることはできる。ストーリーが語られるのは、常に未来においてである。』
天も味方して、ナイジェリアと日本がともに最終戦に勝ち、両者が決勝トーナメントに進出した時、それまでの試合で、シュートがバーを叩いたこともオウン・ゴールも、日本が予選リーグ敗退に終わった要因としての意味ではなく、乗り越えられたハードルとしての意味を持つことになる。そして、意味を書き換えることができる立場にいるのは、直接的には、私たちを代表してリオで戦っているオリンピック・チームである。
頑張れ、日本!
試合前、民放テレビでは、「ひどい試合で1-0で勝つよりは、美しい試合で2-3で負けるほうが良い」というような内容の、クライフの言葉を画面で流していた。ナイジェリア戦を1-0で勝つより、4-5で負けたほうが良いとでも言うかのように。これを見た瞬間、チャンネルをNHKのBS1に変えてしまった。クライフの言葉は、常に美しいサッカーで勝ち続けているチームが、たまに2-3で負けた時にだけ重みがある言葉だろうと私は思う。メダルに近づくためには初戦の勝利がなにより大切であると監督自身が話していた試合を、4-5で負けた試合の後で紹介する言葉では決してないと私は思う。
コロンビア戦、0-2とリードされた後、浅野のゴールで1-2とした時、NHKのアナウンサーは、「これが日本の底力だ!」と叫んだ。私は、その言葉は、3-2に逆点した時にいうことだろうと思ってしまった。なぜ、「1点では意味がない、早く次の1点を取れ、逆点して日本の底力を見せてくれ!」と叫ばないのだろうか。
試合の最終盤、南野の浮き球のパスを浅野が胸でコントロールし、シュートを打とうとしたところ、前に出てきたGKと接触してゴールがならなかったシーンで、解説者が南野のパスの素晴らしさと、浅野のコントロールの絶妙さを褒めていた。きれいなシーンには違いなかったが、試合当事国の放送としては、素晴らしいプレーを褒めるのではなく、それがゴールにつながらなかったことの残念さを、まずは口にしてほしかった。それが応援するということだろう。
この大会が、振り返ってみれば、“あの1点、この1点”ということにならなければよいのにと心から思う。スウェーデンに負けてしまえば、そんな言葉にさえならないのであるが、コロンビアがナイジェリアに引き分けたのに、日本がスウェーデンに引き分けてしまった場合など、「あのシーンのあの失点がなかったら」とか、「このシーンでシュートが決まっていたら」とかいう言葉が出てきてしまう結果にならなければよいのにと思う。
『過去の事実を変えることはできない。しかし、過去の事実の意味を変えることはできる。ストーリーが語られるのは、常に未来においてである。』
天も味方して、ナイジェリアと日本がともに最終戦に勝ち、両者が決勝トーナメントに進出した時、それまでの試合で、シュートがバーを叩いたこともオウン・ゴールも、日本が予選リーグ敗退に終わった要因としての意味ではなく、乗り越えられたハードルとしての意味を持つことになる。そして、意味を書き換えることができる立場にいるのは、直接的には、私たちを代表してリオで戦っているオリンピック・チームである。
頑張れ、日本!
Posted by Okuno at
17:28
│Comments(0)
2016年08月05日
リオ・オリンピック ナイジェリア戦を観て
リオ・オリンピックの初戦、ナイジェリア戦は4-5で敗れた。
この敗戦で感じたことをメモしておこうと思う。
1.日本DFを背中に受けたナイジェリア選手にボールが入った時の、日本側のディフェンスがなぜあんなに弱いのか。
日本の選手が二人で対応しても突破される場面が再三あった。縦パスが入った時の相手と日本の力の差を事前に想定していなかったのか。相手がそんな強みを持っていることを情報として持っていなかったのか。対応を準備していても、それでもやられたのか。準備をしていたが、それでも選手が本番の試合で対応できなかったのか。その辺りは、私たちテレビ観戦者には分からない。しかし、特に前半はあまりにもやられすぎたように思う。
そもそも、試合開始からの日本の守備のように、前線からプレスをかけていけば、相手は縦のロング・ボールを入れてくることは、私でも想定できる。そのロング・ボールから突破されていては、ゲーム・プランが成り立たない。
2.1点リードされて終わった前半。なぜ、同じメンバーのまま後半をスタートさせたのか?
「初戦勝てばメダルに近づき、初戦落とせばメダルは遠のく」と監督が話していたと、テレビの解説で言っていた。それが事実なら、そんなに大事な初戦の前半をリードされて終わったら、後半スタートから選手交代の勝負(賭け)に出るべきだったと思う。それとも、選手を交代しないことで勝負(賭け)に出たのだろうか。
結果論だが(しかし、勝負はすべて結果論だ。強いものが勝つのではなく、勝ったものが強いのだ、という言葉もあるのだから)、交代で出場した、浅野と鈴木の二人は活躍して、2点を追い上げる要因となっていたことを考えると、後半の頭から交代していたら状況が変わっていた可能性が高いと思うのは、私の他にも多いと思う。
「勝負師」と言われた手倉森監督の勝負勘が鈍ったのか、交代しないことで勝負に出たのか、テレビ観戦者の私は知りたい。
3.終盤2点を奪い追い上げたが。
終盤、明らかに足の止まったナイジェリアから、日本は2点を奪って追い上げた。勝負がほとんど決まってしまってからでも、追い上げた頑張りは凄い。試合後の監督インタビューであそこで追い上げないと日本ではないという趣旨の話をしていたと思う。しかし、その凄さが、なぜ、1対1に追いついた後の逆点、2対2に追いついた後の逆点、後半の早い時間の同点および逆点に表れないのだろうか。
他国のチームなら、代表の試合で、もし2-5の状況になってしまったら、闘争心を失って無気力な試合になってしまうのだろうか。私はそうは思わない。なぜなら、その選手たちには代表選手としての誇りや責任感と、プロフェッショナルとしての評価への恐れから、やはり全力を尽くしてプレーを続けると思う。
テレビの前にいた私が、日本代表の選手たちから感じたのは、そうした要素よりは、日本人としての特質(真面目さ)であった。それは、日本の強みであると同時に、現時点での日本サッカーの限界であるようにも、なんとなく感じてしまう。
4.久保選手が出場できなかった。
久保選手が所属チームの意向で出場できなかったことが、敗因の一つであるかどうかは、私には分からない。しかし、日本代表チームの構想が狂ったことは確かだろう。ネット上の記事では、日本協会の幹部が、所属クラブがオリンピックの重要性を理解していない、というようなことが載っていた。
私は、“所属クラブがオリンピックの重要性を理解していない”ことを、日本協会の幹部が理解していないのは、なぜだろうと思う。そのような仕組みのところには完全に素人の私の感想など全くの的外れかもしれないが、日本中のサッカー・プレーヤーを隅々まで統括し、すべての登録会員から登録料等を完璧に徴収する巨大で強大な組織となった日本協会が世界中に張り巡らせた情報網をもってしても、今回のような可能性は事前に想定できなかったのだろうか。
所属クラブからの派遣拒否を受けて、急きょ、幹部が所属クラブに交渉に赴くというようなことは醜態だと感じてしまう。前もって、所属クラブと派遣について特別な契約を結ぶとか、所属クラブの状況から考えて派遣拒否の可能性を考えて、前もって次善の策を考えておくというような対応はできなかったのかと疑問に思ってしまう。
以上、観戦を終えて昼食を食べながら考えたことを、試合終了後3時間というタイミングで記したので、的外れの点もあるかと思うが、私にはすべて現時点での日本サッカーの諸問題として感じられたことを思うままに記しておきます。
みなさん、試合を観て、どんなことを感じましたか。日本サッカーの発展ために、また、話し合いましょう。
この敗戦で感じたことをメモしておこうと思う。
1.日本DFを背中に受けたナイジェリア選手にボールが入った時の、日本側のディフェンスがなぜあんなに弱いのか。
日本の選手が二人で対応しても突破される場面が再三あった。縦パスが入った時の相手と日本の力の差を事前に想定していなかったのか。相手がそんな強みを持っていることを情報として持っていなかったのか。対応を準備していても、それでもやられたのか。準備をしていたが、それでも選手が本番の試合で対応できなかったのか。その辺りは、私たちテレビ観戦者には分からない。しかし、特に前半はあまりにもやられすぎたように思う。
そもそも、試合開始からの日本の守備のように、前線からプレスをかけていけば、相手は縦のロング・ボールを入れてくることは、私でも想定できる。そのロング・ボールから突破されていては、ゲーム・プランが成り立たない。
2.1点リードされて終わった前半。なぜ、同じメンバーのまま後半をスタートさせたのか?
「初戦勝てばメダルに近づき、初戦落とせばメダルは遠のく」と監督が話していたと、テレビの解説で言っていた。それが事実なら、そんなに大事な初戦の前半をリードされて終わったら、後半スタートから選手交代の勝負(賭け)に出るべきだったと思う。それとも、選手を交代しないことで勝負(賭け)に出たのだろうか。
結果論だが(しかし、勝負はすべて結果論だ。強いものが勝つのではなく、勝ったものが強いのだ、という言葉もあるのだから)、交代で出場した、浅野と鈴木の二人は活躍して、2点を追い上げる要因となっていたことを考えると、後半の頭から交代していたら状況が変わっていた可能性が高いと思うのは、私の他にも多いと思う。
「勝負師」と言われた手倉森監督の勝負勘が鈍ったのか、交代しないことで勝負に出たのか、テレビ観戦者の私は知りたい。
3.終盤2点を奪い追い上げたが。
終盤、明らかに足の止まったナイジェリアから、日本は2点を奪って追い上げた。勝負がほとんど決まってしまってからでも、追い上げた頑張りは凄い。試合後の監督インタビューであそこで追い上げないと日本ではないという趣旨の話をしていたと思う。しかし、その凄さが、なぜ、1対1に追いついた後の逆点、2対2に追いついた後の逆点、後半の早い時間の同点および逆点に表れないのだろうか。
他国のチームなら、代表の試合で、もし2-5の状況になってしまったら、闘争心を失って無気力な試合になってしまうのだろうか。私はそうは思わない。なぜなら、その選手たちには代表選手としての誇りや責任感と、プロフェッショナルとしての評価への恐れから、やはり全力を尽くしてプレーを続けると思う。
テレビの前にいた私が、日本代表の選手たちから感じたのは、そうした要素よりは、日本人としての特質(真面目さ)であった。それは、日本の強みであると同時に、現時点での日本サッカーの限界であるようにも、なんとなく感じてしまう。
4.久保選手が出場できなかった。
久保選手が所属チームの意向で出場できなかったことが、敗因の一つであるかどうかは、私には分からない。しかし、日本代表チームの構想が狂ったことは確かだろう。ネット上の記事では、日本協会の幹部が、所属クラブがオリンピックの重要性を理解していない、というようなことが載っていた。
私は、“所属クラブがオリンピックの重要性を理解していない”ことを、日本協会の幹部が理解していないのは、なぜだろうと思う。そのような仕組みのところには完全に素人の私の感想など全くの的外れかもしれないが、日本中のサッカー・プレーヤーを隅々まで統括し、すべての登録会員から登録料等を完璧に徴収する巨大で強大な組織となった日本協会が世界中に張り巡らせた情報網をもってしても、今回のような可能性は事前に想定できなかったのだろうか。
所属クラブからの派遣拒否を受けて、急きょ、幹部が所属クラブに交渉に赴くというようなことは醜態だと感じてしまう。前もって、所属クラブと派遣について特別な契約を結ぶとか、所属クラブの状況から考えて派遣拒否の可能性を考えて、前もって次善の策を考えておくというような対応はできなかったのかと疑問に思ってしまう。
以上、観戦を終えて昼食を食べながら考えたことを、試合終了後3時間というタイミングで記したので、的外れの点もあるかと思うが、私にはすべて現時点での日本サッカーの諸問題として感じられたことを思うままに記しておきます。
みなさん、試合を観て、どんなことを感じましたか。日本サッカーの発展ために、また、話し合いましょう。
Posted by Okuno at
15:37
│Comments(0)