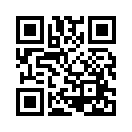2016年11月17日
2016全少県大会観戦記
優勝候補にも名前が挙げられていた“KFCジュニア”であったが、準々決勝戦で“PK戦”の結果、惜しくも敗退した。
対戦相手のアルテリーヴォ湯浅に対して、全般的には押し気味に試合を進めたが、前半DFラインの背後に出されたバウンドボールに反応して飛び出したGKより一瞬先に相手FWに触られ失点した。対戦前から、ひょっとしたら事実上の決勝戦になるのではないかと予想していたが、実際、チーム力は拮抗していたと思う。そのような相手に対して、トーナメント戦で先取点を奪われるとたいへん厳しいゲーム展開になるものだか、我がKFCジュニアは焦ることもなく落ち着いて試合を進め、後半早々に相手と同じような展開から同点に追いついたのはさすがであった。ただ、やはり先取点は重く、逆転するところまでは至らなかった。
長いサッカー人生を歩き始めた少年プレーヤーの試合の敗因を考えても益するところはなにもないと思う。そうではなくて、クラブとしてさらにレベル・アップしていくための材料として、どんなことを目指していけば良いのかは考えなくてはならないと思う。長年、クラブの運営に関わってきて思うのは、今年のジュニアはクラブ史上最強のチームであったということだ。これは、プレーヤーの資質、スタッフのチーム作りに費やした努力、保護者の支援などの総合力の賜物である。
勝ち進めなかった要因(敗因ではない)はどこにあったのだろうか。サッカーは対戦相手のあることである。アルテリーヴォ湯浅には、たぶん今年県内最高のプレーヤーを中心にしたチームである。その湯浅チームの一人一人が必死になって体を張って、体を投げ出して、カバーしあってボールを奪いに来た。その相手に対してでも、押し気味に試合を進める力が今年のジュニアにはあった。ただ、その相手を崩し切る力まではなかったということだと思っている。
クラブとしてどう取り組んでいくべきかはスタッフ全員で知恵を絞って考えていかなくてはならないが、その材料として私が考えているのは次のようなことだ。相手のプレーヤーどうしのカバーリングが効きにくいような状況を作り出すために、ポゼッションのレベルをさらに上げていく。そうして、1対1や数的優位の状況を作り出し、そこを突破できる個人技に磨きをかける。もう一つは、ワンタッチ・パスを使って突破するグループ力を養う。オーソドックスな方法はこのようなものだと思う。奇をてらったような方法論は、プレーヤーの成長を阻害するかもしれないし、クラブの指導力も成長しないと思う。
試合後に私が感じた残念さや脱力感以上のものが、プレーヤー、保護者、スタッフには突き刺さったことだと思う。試合結果については、「これもサッカーだ」という他はない。“敗戦を受け入れる”とは、どういうことだろうか。負けてもどうってことはないと開き直ることではもちろんない。サッカーをやめてしまうことでも当然ない。“敗戦を受け入れる”ことはそれなりに難しい。地区予選で敗退したチームのほうが多い。県大会で優勝するのは、32チーム中1チームだけである。県大会で優勝しても、全国大会で大半のチームはどこかで負ける。プロになっても同じである。サッカーはほとんどどこかで負けるものだ。たとえ世界一になっても、いつかはその地位を失う。負けるのが嫌なら、サッカーをやらないほうが良い。サッカーをやらなければ、サッカーで負けることはない。しかし、負けることに平気になってもサッカーをやる意味がない。なぜなら、サッカーは勝ちを目指すことを基盤に成り立っているものだからである。
サッカーとは勝つことを目指してトレーニングに励み、試合に勝った時はみんなと一緒になって喜び、試合結果が思わしくなかったときは失意に沈み、それでもまた次に勝つことを目指してトレーニングに戻っていく。それがサッカーを愛するということだと思う。それは、世界的なクラブであっても、少年チームであっても本質的に同じである。
試合中の一つ一つのプレーをドキドキしながら見守り、一喜一憂しながら歓声を上げ、ため息をもらす。それらのシーンは、瞬間に現れ、次の瞬間には消えていく。残るのは試合結果だけである。しかし、そのプレーの一瞬一瞬にこそサッカーの喜びがある。これは、『フットボールの新世紀 美と快楽の身体』(今福龍太著、廣済堂出版、2001年刊)に書かれていることである。
あの試合に臨んだプレーヤー、スタッフ、それを見守った保護者、わたしのようなクラブ関係者、その場に居合わせた全員が、その至福の一瞬一瞬を体験したのだと私は確信している。そうであれば、“敗戦を受け入れる”とは、そもそも意味のない言葉かもしれない。サッカーの本質は、試合の結果にあるのではない。一瞬一瞬のプレーに恍惚とするところにある。しかし、一方で私たちは少しでも高みを目指して奮闘し続けなければならない。それがサッカーを愛するということだと私は思う。
KFCジュニアのみなさん、素晴らしい一瞬一瞬をありがとう。
奥野修造
対戦相手のアルテリーヴォ湯浅に対して、全般的には押し気味に試合を進めたが、前半DFラインの背後に出されたバウンドボールに反応して飛び出したGKより一瞬先に相手FWに触られ失点した。対戦前から、ひょっとしたら事実上の決勝戦になるのではないかと予想していたが、実際、チーム力は拮抗していたと思う。そのような相手に対して、トーナメント戦で先取点を奪われるとたいへん厳しいゲーム展開になるものだか、我がKFCジュニアは焦ることもなく落ち着いて試合を進め、後半早々に相手と同じような展開から同点に追いついたのはさすがであった。ただ、やはり先取点は重く、逆転するところまでは至らなかった。
長いサッカー人生を歩き始めた少年プレーヤーの試合の敗因を考えても益するところはなにもないと思う。そうではなくて、クラブとしてさらにレベル・アップしていくための材料として、どんなことを目指していけば良いのかは考えなくてはならないと思う。長年、クラブの運営に関わってきて思うのは、今年のジュニアはクラブ史上最強のチームであったということだ。これは、プレーヤーの資質、スタッフのチーム作りに費やした努力、保護者の支援などの総合力の賜物である。
勝ち進めなかった要因(敗因ではない)はどこにあったのだろうか。サッカーは対戦相手のあることである。アルテリーヴォ湯浅には、たぶん今年県内最高のプレーヤーを中心にしたチームである。その湯浅チームの一人一人が必死になって体を張って、体を投げ出して、カバーしあってボールを奪いに来た。その相手に対してでも、押し気味に試合を進める力が今年のジュニアにはあった。ただ、その相手を崩し切る力まではなかったということだと思っている。
クラブとしてどう取り組んでいくべきかはスタッフ全員で知恵を絞って考えていかなくてはならないが、その材料として私が考えているのは次のようなことだ。相手のプレーヤーどうしのカバーリングが効きにくいような状況を作り出すために、ポゼッションのレベルをさらに上げていく。そうして、1対1や数的優位の状況を作り出し、そこを突破できる個人技に磨きをかける。もう一つは、ワンタッチ・パスを使って突破するグループ力を養う。オーソドックスな方法はこのようなものだと思う。奇をてらったような方法論は、プレーヤーの成長を阻害するかもしれないし、クラブの指導力も成長しないと思う。
試合後に私が感じた残念さや脱力感以上のものが、プレーヤー、保護者、スタッフには突き刺さったことだと思う。試合結果については、「これもサッカーだ」という他はない。“敗戦を受け入れる”とは、どういうことだろうか。負けてもどうってことはないと開き直ることではもちろんない。サッカーをやめてしまうことでも当然ない。“敗戦を受け入れる”ことはそれなりに難しい。地区予選で敗退したチームのほうが多い。県大会で優勝するのは、32チーム中1チームだけである。県大会で優勝しても、全国大会で大半のチームはどこかで負ける。プロになっても同じである。サッカーはほとんどどこかで負けるものだ。たとえ世界一になっても、いつかはその地位を失う。負けるのが嫌なら、サッカーをやらないほうが良い。サッカーをやらなければ、サッカーで負けることはない。しかし、負けることに平気になってもサッカーをやる意味がない。なぜなら、サッカーは勝ちを目指すことを基盤に成り立っているものだからである。
サッカーとは勝つことを目指してトレーニングに励み、試合に勝った時はみんなと一緒になって喜び、試合結果が思わしくなかったときは失意に沈み、それでもまた次に勝つことを目指してトレーニングに戻っていく。それがサッカーを愛するということだと思う。それは、世界的なクラブであっても、少年チームであっても本質的に同じである。
試合中の一つ一つのプレーをドキドキしながら見守り、一喜一憂しながら歓声を上げ、ため息をもらす。それらのシーンは、瞬間に現れ、次の瞬間には消えていく。残るのは試合結果だけである。しかし、そのプレーの一瞬一瞬にこそサッカーの喜びがある。これは、『フットボールの新世紀 美と快楽の身体』(今福龍太著、廣済堂出版、2001年刊)に書かれていることである。
あの試合に臨んだプレーヤー、スタッフ、それを見守った保護者、わたしのようなクラブ関係者、その場に居合わせた全員が、その至福の一瞬一瞬を体験したのだと私は確信している。そうであれば、“敗戦を受け入れる”とは、そもそも意味のない言葉かもしれない。サッカーの本質は、試合の結果にあるのではない。一瞬一瞬のプレーに恍惚とするところにある。しかし、一方で私たちは少しでも高みを目指して奮闘し続けなければならない。それがサッカーを愛するということだと私は思う。
KFCジュニアのみなさん、素晴らしい一瞬一瞬をありがとう。
奥野修造
Posted by Okuno at
11:23
│Comments(0)
2016年11月03日
2016ソラティオーラ・コーチング研修会 報告
報告者 奥野修造
実施日 2016年10月29日(土)・30日(日)
会 場 海南スポーツセンター
参加者 10月29日(土)13人、30日(日)15人
以下に、二日間にわたって実施した研修会で話し合った内容について、箇条書きで報告する。
「ポゼッション」をテーマにしたトレーニング
◇年少期のスキルを中心にしたトレーニングから、いつ、どのようにしてポゼッションのトレーニングを始めていくべきか、今模索している。
◇スキルとポゼッションの練習比率は、年代によってどれくらいを目安にすれば、プレーヤーの成長を支えていけるのだろうか。
◇練習中、“ストップ”の声で練習を中断して指導しすぎていないか、また、いろいろな要素について指導しすぎていないか。うまくいっていない状況が続いても、ある程度の時間は練習を中断しないで継続することも必要ではないか。
◇パスの受け手の遠い足のインサイドへパスを出すこと、受け手はボールから遠い足のインサイドでコントロールできるようポジションを取り、体の向きを準備することは、ポゼッション・トレーニングの基本中の基本である。年少期から徹底して指導し続けることが大切だ。
◇ポゼッション・トレーニングは、チームでボールを保持し続けることが目的ではない。何のための保持か、実際のゲームの展開に必要などんな要素をテーマにしたポゼッション・トレーニングなのか、テーマに沿ったメニューにする必要がある。
◇エリアのライン上にフリーマンを置いたトレーニングでは、フリーマンの重要性を理解しよう。全体を見渡し、次の展開を予測し、ボールを要求して組み立てる。このような役割を身につけるには、エリアの中に入ってマークを受けながら360度視野に入れることが要求されるより、フリーマンのほうがはるかに身につけやすい。
「突破」をテーマにしたトレーニング
◇自エンドで2対2、相手エンドで2対2として、縦パスを入れることで突破のスイッチとする練習メニューは、スムーズにいかないことが多い。攻撃役の前の2人が、ボールを受ける前の準備、縦パスが入るタイミングの見極め方などいろいろな要素が絡んでくるからだ。もっと単純な練習メニューを工夫していきたい。
◇「突破の基本はワン・ツーである」ことは、サッカーの永遠の真理である。しかし、あまり、というか、ほとんど突き詰めた練習ができていない。指導してみれば、ワン・ツーの奥深さや指導のむずかしさがコーチにも理解できるはずだ。各チームで取り組んでいこう。
◇「ワン・ツー」は、相手ペナルティー・エリア近くでやるのが効果的である。
◇グループでの突破には、その準備段階として、“仕掛け”が必要だ。“仕掛け”には、フリーランとドリブルがある。
◇突破の練習メニューは、成功率をどれくらいにイメージして設定するのが適切なのだろうか。
◇トレーニングではできるようになっても、ゲームではその成果が表れないことがある。トレーニングとゲームをつなげるには、どんな工夫が必要なのか。
ゴールキーパー・トレーニング
指導者 池田佳津彦氏
受講者 セッションⅠ=小学4・5年生 7人
セッションⅡ=小学6年生~中学2年生 4人
◇まずは、基本の構えとオーバーハンド・キャッチ、アンダーハンド・キャッチから指導しよう。
◇週1回15分程度のキーパー練習から始めよう。
ゲーム分析
◇チームの攻撃パターンを作ろう。どのエリアを、誰がどんな役割で、どんな方法で突破を図るのかを、チームの共通理解として持てば、プレーヤーの連動した動きにつながる。
◇チームの中で、比較的弱いパートを攻撃パターンの中にどう組み入れるのかを工夫しなければいけない。プレーヤーに能力以上を要求してはいけない。各プレーヤーの特徴と資質を生かした攻撃パターンを工夫しなくてはいけない。
◇システムがすべてを決めるわけではないが、両チームのシステムのズレを、コーチは考えなくてはいけない。両チームのシステムがズレているとき、それが自分のチームに有利に作用しているのか、不利に作用しているのかを見極めて対応する必要がある。
◇KFCソラティオーラとKFCジュニアの連動した詰めの速さは、他のカテゴリーでも取り入れていきたい。県大会上位では、必要とされる基準であろうし、チームのレベル・アップには当然要求される要素である。
◇ドリブル突破、スペースへのパス、だけではないチームとしての突破のパターンを作っていくことが、相手チームの速いプレスを打ち破る力になる。
◇ソラティオーラU-12のチームに要求されるのは、相手ボール保持者への距離を詰めていく守備である。プレッシャーをかけられない間合いでポジションを取っても守備にはならない。1対1の守備のできないプレーヤーが、1対2の守備はできない。人数が多くても抜かれるだけである。
◇最終ラインの守備のカバーリングが甘い。センターバックが1対1で負けた時の対応が不足している。
◇個々の力が上回る相手に対して、どのような守備で挑むか、その結果をどう受け入れるかは工夫しなくてはいけない。
◇U-14チームは、次のポジションへの動き出しが遅く、ゆっくりとしている。早く、次のポジションを取ることの重要性を理解させ、ポゼッション・トレーニングを通じて、そのことを身につけていく必要がある。
全体的な総括
このような規模での研修会は初めてのことであったが、外部から権威を持った指導者にアドバイスを請うといった形式ではなく、日々実際のプレーヤーを相手に実施しているトレーニング内容を紹介し、それについて、でさらにレベル・アップしていくにはどんな工夫ができるのかという観点から、自分たちで意見を交換し合うという形での研修会は、たいへん意義のあるものであったと考えている。
上にまとめた課題について、それぞれのコーチがこれからの日々のトレーニングとゲームの中で、悩み、考え、試行錯誤を重ね、少しずつ自分のコーチとしての力量を高めていき、クラブの発展につなげていこうとする実践を続けていきたい。
クラブとして、一貫した指導方針を持つことは当然大切なことだが、一方でどのコーチも同じ指導をしていたのでは、仮にその指導方法に問題があった場合、クラブ全体として他のクラブに後れを取ることになる。また、ある種の“全体主義”のような、およそサッカーらしくなくなってしまう恐れもある。クラブの中に、ある種の異質なものを持った指導者がいることも、クラブの中に多様性を持つことになり、そのことが、クラブの強靭さや健全性を確保していくことにつながると思う。クラブとしての共通した指導方針と、コーチの個性を併せ持ったクラブを目指していきたい。
次回は、話し合いの中でも出た、「ワン・ツーを使った突破」をワン・テーマとしたコーチング研修会を実施したい。それまでに各年代・各カテゴリーでテーマに沿ったトレーニングを積み重ね、研修会に持ち寄って工夫を話し合い、クラブ全体の指導力をレベル・アップしていきたい。
実施日 2016年10月29日(土)・30日(日)
会 場 海南スポーツセンター
参加者 10月29日(土)13人、30日(日)15人
以下に、二日間にわたって実施した研修会で話し合った内容について、箇条書きで報告する。
「ポゼッション」をテーマにしたトレーニング
◇年少期のスキルを中心にしたトレーニングから、いつ、どのようにしてポゼッションのトレーニングを始めていくべきか、今模索している。
◇スキルとポゼッションの練習比率は、年代によってどれくらいを目安にすれば、プレーヤーの成長を支えていけるのだろうか。
◇練習中、“ストップ”の声で練習を中断して指導しすぎていないか、また、いろいろな要素について指導しすぎていないか。うまくいっていない状況が続いても、ある程度の時間は練習を中断しないで継続することも必要ではないか。
◇パスの受け手の遠い足のインサイドへパスを出すこと、受け手はボールから遠い足のインサイドでコントロールできるようポジションを取り、体の向きを準備することは、ポゼッション・トレーニングの基本中の基本である。年少期から徹底して指導し続けることが大切だ。
◇ポゼッション・トレーニングは、チームでボールを保持し続けることが目的ではない。何のための保持か、実際のゲームの展開に必要などんな要素をテーマにしたポゼッション・トレーニングなのか、テーマに沿ったメニューにする必要がある。
◇エリアのライン上にフリーマンを置いたトレーニングでは、フリーマンの重要性を理解しよう。全体を見渡し、次の展開を予測し、ボールを要求して組み立てる。このような役割を身につけるには、エリアの中に入ってマークを受けながら360度視野に入れることが要求されるより、フリーマンのほうがはるかに身につけやすい。
「突破」をテーマにしたトレーニング
◇自エンドで2対2、相手エンドで2対2として、縦パスを入れることで突破のスイッチとする練習メニューは、スムーズにいかないことが多い。攻撃役の前の2人が、ボールを受ける前の準備、縦パスが入るタイミングの見極め方などいろいろな要素が絡んでくるからだ。もっと単純な練習メニューを工夫していきたい。
◇「突破の基本はワン・ツーである」ことは、サッカーの永遠の真理である。しかし、あまり、というか、ほとんど突き詰めた練習ができていない。指導してみれば、ワン・ツーの奥深さや指導のむずかしさがコーチにも理解できるはずだ。各チームで取り組んでいこう。
◇「ワン・ツー」は、相手ペナルティー・エリア近くでやるのが効果的である。
◇グループでの突破には、その準備段階として、“仕掛け”が必要だ。“仕掛け”には、フリーランとドリブルがある。
◇突破の練習メニューは、成功率をどれくらいにイメージして設定するのが適切なのだろうか。
◇トレーニングではできるようになっても、ゲームではその成果が表れないことがある。トレーニングとゲームをつなげるには、どんな工夫が必要なのか。
ゴールキーパー・トレーニング
指導者 池田佳津彦氏
受講者 セッションⅠ=小学4・5年生 7人
セッションⅡ=小学6年生~中学2年生 4人
◇まずは、基本の構えとオーバーハンド・キャッチ、アンダーハンド・キャッチから指導しよう。
◇週1回15分程度のキーパー練習から始めよう。
ゲーム分析
◇チームの攻撃パターンを作ろう。どのエリアを、誰がどんな役割で、どんな方法で突破を図るのかを、チームの共通理解として持てば、プレーヤーの連動した動きにつながる。
◇チームの中で、比較的弱いパートを攻撃パターンの中にどう組み入れるのかを工夫しなければいけない。プレーヤーに能力以上を要求してはいけない。各プレーヤーの特徴と資質を生かした攻撃パターンを工夫しなくてはいけない。
◇システムがすべてを決めるわけではないが、両チームのシステムのズレを、コーチは考えなくてはいけない。両チームのシステムがズレているとき、それが自分のチームに有利に作用しているのか、不利に作用しているのかを見極めて対応する必要がある。
◇KFCソラティオーラとKFCジュニアの連動した詰めの速さは、他のカテゴリーでも取り入れていきたい。県大会上位では、必要とされる基準であろうし、チームのレベル・アップには当然要求される要素である。
◇ドリブル突破、スペースへのパス、だけではないチームとしての突破のパターンを作っていくことが、相手チームの速いプレスを打ち破る力になる。
◇ソラティオーラU-12のチームに要求されるのは、相手ボール保持者への距離を詰めていく守備である。プレッシャーをかけられない間合いでポジションを取っても守備にはならない。1対1の守備のできないプレーヤーが、1対2の守備はできない。人数が多くても抜かれるだけである。
◇最終ラインの守備のカバーリングが甘い。センターバックが1対1で負けた時の対応が不足している。
◇個々の力が上回る相手に対して、どのような守備で挑むか、その結果をどう受け入れるかは工夫しなくてはいけない。
◇U-14チームは、次のポジションへの動き出しが遅く、ゆっくりとしている。早く、次のポジションを取ることの重要性を理解させ、ポゼッション・トレーニングを通じて、そのことを身につけていく必要がある。
全体的な総括
このような規模での研修会は初めてのことであったが、外部から権威を持った指導者にアドバイスを請うといった形式ではなく、日々実際のプレーヤーを相手に実施しているトレーニング内容を紹介し、それについて、でさらにレベル・アップしていくにはどんな工夫ができるのかという観点から、自分たちで意見を交換し合うという形での研修会は、たいへん意義のあるものであったと考えている。
上にまとめた課題について、それぞれのコーチがこれからの日々のトレーニングとゲームの中で、悩み、考え、試行錯誤を重ね、少しずつ自分のコーチとしての力量を高めていき、クラブの発展につなげていこうとする実践を続けていきたい。
クラブとして、一貫した指導方針を持つことは当然大切なことだが、一方でどのコーチも同じ指導をしていたのでは、仮にその指導方法に問題があった場合、クラブ全体として他のクラブに後れを取ることになる。また、ある種の“全体主義”のような、およそサッカーらしくなくなってしまう恐れもある。クラブの中に、ある種の異質なものを持った指導者がいることも、クラブの中に多様性を持つことになり、そのことが、クラブの強靭さや健全性を確保していくことにつながると思う。クラブとしての共通した指導方針と、コーチの個性を併せ持ったクラブを目指していきたい。
次回は、話し合いの中でも出た、「ワン・ツーを使った突破」をワン・テーマとしたコーチング研修会を実施したい。それまでに各年代・各カテゴリーでテーマに沿ったトレーニングを積み重ね、研修会に持ち寄って工夫を話し合い、クラブ全体の指導力をレベル・アップしていきたい。
Posted by Okuno at
16:23
│Comments(0)