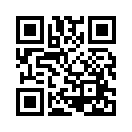2018年05月14日
ビッグ・バン
5月13日(日)、まだ雨の残る中傘を差し、試合の余韻に浸りながら紀三井寺陸上競技場から駐車場へ歩いている時に、私の心に浮かんできたのは“ビッグ・バン”という言葉だった。
天皇杯県予選決勝戦、アルテリーヴォに1点リードされ試合終了まで5分を切っていたと思う。相手ゴールに向かって左側ペナルティー・エリア角からそんなに遠くない地点で得たフリー・キックをヘディング・シュート。ゴール・キーパーが左に倒れながらなんとか防いだもののルーズ・ボールとなってこぼれたボールをゴール・エリア内から押し込んでゴール。
昼前から雨が強くなる中、クラブの代表として応援にいかなくてはと思い、悪天候のためにやや気持ちが進まないまま(ごめんなさい!)に家を出たが、試合開始直前のスタンドに入った時、自分の目を疑い、一気に気持ちが高ぶって来た。何百人という多くの人が、この雨の中応援に来てくれていたのだ。エスコート・キッズを務めてくれた子どもたちと保護者、大会が中止になったため急きょ応援に来てくれた3・4年生の子どもたちと保護者、練習を終えてから、または練習試合の後、会場に来てくれた小学校高学年の選手やエンジェルスの選手たちとスタッフ、試合に出場する選手の家族や知り合いの方。本当にありがとうございました。トップ・チームの選手たちにはとてつもない力となったことでしょう。
スローモーションを見ているかのように、ゴール・エリアの中で誰の支配も受けずに自由にゆっくり転がっている直径20㎝あまりの球体に一番先に触れたのは、白いアウェーのユニフォームに身を包んだ我が海南FCの選手だった。倒れたまま、なおもゴールを死守すべく伸ばしたゴール・キーパーの左手の指先と、なんの感情も持たずに次の瞬間を見守っているかのように泰然と直立している白いゴール・ポストのわずかな間隔を、自分に最初に触れてくれた選手の意志をそのままに受け入れたボールが通り抜けた、まさにその瞬間に“ビッグ・バン”は起こった。
およそ1,000の瞳が、誰の指示もなく無機質なボールに焦点を合わせる。その視線に込められた思いを喜んで受け入れたかのようにまるで生命体のように自らの意志で白いゴール・ラインを通り過ぎた。その瞬間、両手を突き上げる者、立ち上がり大声を発する者。その場に居合わせた全員が瞬時に“ビッグ・バン”を創出させたのだ。プレーする者と応援する者という関係ではなく、お互いに名前も知らない観戦者という各個人という存在ではなく、ゴールの瞬間の喜びを共有する“場”を、それまでの時の流れとは無関係に、まさに突然に創出させたのだ。
チームのよって立つ基盤、プレーヤーの来歴・社会的地位・家族関係、応援に来てくれた人の抱えているはずの事情、そんな諸々の背景やここに至るまでの個々の経緯を、誰の意志もコントロールもなく瞬時に“無”にし、膨大なエネルギーを瞬時に一斉に放出し、サッカーの喜びの宇宙を創出する“ビッグ・バン”を私たちは共有し、経験することができた。これを至福と言わずなんと言うか。
サッカーの、そして多分スポーツの本当の物凄さは、その瞬間にある。
私は、そのことをある本を読んで知識としては知っていた。
『フットボールの新世紀 美と快楽の身体』(今福龍太 著、廣済堂出版、2001年発行)から紹介する。
- 「結果」ではなく、ましてや「過程」でもなく、私がサッカーで愛したいのは「いま」である。時の流れ、感情の流れ、思考のとどまることなき流れの中で明滅し、閃光を発し、たちまちにして消え去る「現在」という、瞬時の強度に満ちた生々しい「いま」そのものである。「いま」が時の深みを生み出し、プレーヤーの身体的アートに厚みをもたらすという事実への、無私の愛である。-
写真もない、硬い文章になりましたが、たまにはこんなことを考えてみるのも、また、サッカーの楽しみだと思います。
天皇杯県予選決勝戦、アルテリーヴォに1点リードされ試合終了まで5分を切っていたと思う。相手ゴールに向かって左側ペナルティー・エリア角からそんなに遠くない地点で得たフリー・キックをヘディング・シュート。ゴール・キーパーが左に倒れながらなんとか防いだもののルーズ・ボールとなってこぼれたボールをゴール・エリア内から押し込んでゴール。
昼前から雨が強くなる中、クラブの代表として応援にいかなくてはと思い、悪天候のためにやや気持ちが進まないまま(ごめんなさい!)に家を出たが、試合開始直前のスタンドに入った時、自分の目を疑い、一気に気持ちが高ぶって来た。何百人という多くの人が、この雨の中応援に来てくれていたのだ。エスコート・キッズを務めてくれた子どもたちと保護者、大会が中止になったため急きょ応援に来てくれた3・4年生の子どもたちと保護者、練習を終えてから、または練習試合の後、会場に来てくれた小学校高学年の選手やエンジェルスの選手たちとスタッフ、試合に出場する選手の家族や知り合いの方。本当にありがとうございました。トップ・チームの選手たちにはとてつもない力となったことでしょう。
スローモーションを見ているかのように、ゴール・エリアの中で誰の支配も受けずに自由にゆっくり転がっている直径20㎝あまりの球体に一番先に触れたのは、白いアウェーのユニフォームに身を包んだ我が海南FCの選手だった。倒れたまま、なおもゴールを死守すべく伸ばしたゴール・キーパーの左手の指先と、なんの感情も持たずに次の瞬間を見守っているかのように泰然と直立している白いゴール・ポストのわずかな間隔を、自分に最初に触れてくれた選手の意志をそのままに受け入れたボールが通り抜けた、まさにその瞬間に“ビッグ・バン”は起こった。
およそ1,000の瞳が、誰の指示もなく無機質なボールに焦点を合わせる。その視線に込められた思いを喜んで受け入れたかのようにまるで生命体のように自らの意志で白いゴール・ラインを通り過ぎた。その瞬間、両手を突き上げる者、立ち上がり大声を発する者。その場に居合わせた全員が瞬時に“ビッグ・バン”を創出させたのだ。プレーする者と応援する者という関係ではなく、お互いに名前も知らない観戦者という各個人という存在ではなく、ゴールの瞬間の喜びを共有する“場”を、それまでの時の流れとは無関係に、まさに突然に創出させたのだ。
チームのよって立つ基盤、プレーヤーの来歴・社会的地位・家族関係、応援に来てくれた人の抱えているはずの事情、そんな諸々の背景やここに至るまでの個々の経緯を、誰の意志もコントロールもなく瞬時に“無”にし、膨大なエネルギーを瞬時に一斉に放出し、サッカーの喜びの宇宙を創出する“ビッグ・バン”を私たちは共有し、経験することができた。これを至福と言わずなんと言うか。
サッカーの、そして多分スポーツの本当の物凄さは、その瞬間にある。
私は、そのことをある本を読んで知識としては知っていた。
『フットボールの新世紀 美と快楽の身体』(今福龍太 著、廣済堂出版、2001年発行)から紹介する。
- 「結果」ではなく、ましてや「過程」でもなく、私がサッカーで愛したいのは「いま」である。時の流れ、感情の流れ、思考のとどまることなき流れの中で明滅し、閃光を発し、たちまちにして消え去る「現在」という、瞬時の強度に満ちた生々しい「いま」そのものである。「いま」が時の深みを生み出し、プレーヤーの身体的アートに厚みをもたらすという事実への、無私の愛である。-
写真もない、硬い文章になりましたが、たまにはこんなことを考えてみるのも、また、サッカーの楽しみだと思います。
Posted by Okuno at
11:07
│Comments(0)
2018年05月04日
2018アウトドア・パーティー
普段はカテゴリー別に活動しているソラティオーラの会員が、一堂に会して交流し親睦を深め、クラブの一体感を高める活動が年に2回あります。春の「アウトドア・パーティー」と、秋の「ソラティオーラ・フットボールデー」です。
2018年度のアウトドア・パーティーは、昨年好評だった“黒沢ハイランド”で今年も開催させていただきました。メイ・ストームと呼ばれた前日の雨がいつまで残るかとやきもきしましたが、みんなの気持ちが天に通じたのか、当日朝にはすっかり雨が上がり高原には爽やかな風が吹いていました。(本当に日ごろから良い行いをしておくものですね。天の神様はちゃんと見てくれています。)
気がはやり、集合時間を待ちきれないのか、11:00受付開始と連絡してあったにもかかわらず、一番早い人は9:30過ぎにはすでに会場に到着していました。(アウトドア・パーティーをそんなに楽しみにしてくれているとは、本当にうれしいです。)
今年の参加者は、大人125人、中学生以下の子ども160人、合計285人でした。おそらく、クラブ史上最高の人数であったと思います。ソラティオーラを愛してくれている人がこんなにたくさんいるなんてと感激しています。

中学生たちも火おこしに悪戦苦闘しながらも準備を進めていくのと並行して、12:00ジャストに参加者全員で、「今年もソラティオーラでサッカーを楽しもう」と、クラブ愛を確認しながらの“乾杯!”。ジュージューと音を立てているお肉やソーセージなどの食材をほおばるのを待ちきれません。
お腹が膨らんだ子どもたちは芝生広場へ一目散。芝生滑りやバットとボールを借りて野球に興じる子どもやアーチェリーにチャレンジしている子どももいました。みんな体を動かすのが大好きですね。
そろそろ恒例の“大ビンゴ大会”です。「ビンゴ始めるよ」の一声だけで、広場に散らばっていた子どもたちはいっせいに集まってきます。まるで、牧羊犬に誘導されているかわいい羊たちのようです。
さあ、大興奮のビンゴ大会が始まります。

あっと言う間に半日が過ぎていきました。私たちのアウトドア・パーティーに会場を提供してくれた黒沢ハイランドのご厚意に心から感謝しつつのお開きとなりました。
みなさん、会場をきれいに片づけて帰りましょう。来年もまたここでアウトドア・パーティーやりたいですね。
2018年度のアウトドア・パーティーは、昨年好評だった“黒沢ハイランド”で今年も開催させていただきました。メイ・ストームと呼ばれた前日の雨がいつまで残るかとやきもきしましたが、みんなの気持ちが天に通じたのか、当日朝にはすっかり雨が上がり高原には爽やかな風が吹いていました。(本当に日ごろから良い行いをしておくものですね。天の神様はちゃんと見てくれています。)
気がはやり、集合時間を待ちきれないのか、11:00受付開始と連絡してあったにもかかわらず、一番早い人は9:30過ぎにはすでに会場に到着していました。(アウトドア・パーティーをそんなに楽しみにしてくれているとは、本当にうれしいです。)
今年の参加者は、大人125人、中学生以下の子ども160人、合計285人でした。おそらく、クラブ史上最高の人数であったと思います。ソラティオーラを愛してくれている人がこんなにたくさんいるなんてと感激しています。

中学生たちも火おこしに悪戦苦闘しながらも準備を進めていくのと並行して、12:00ジャストに参加者全員で、「今年もソラティオーラでサッカーを楽しもう」と、クラブ愛を確認しながらの“乾杯!”。ジュージューと音を立てているお肉やソーセージなどの食材をほおばるのを待ちきれません。
お腹が膨らんだ子どもたちは芝生広場へ一目散。芝生滑りやバットとボールを借りて野球に興じる子どもやアーチェリーにチャレンジしている子どももいました。みんな体を動かすのが大好きですね。
そろそろ恒例の“大ビンゴ大会”です。「ビンゴ始めるよ」の一声だけで、広場に散らばっていた子どもたちはいっせいに集まってきます。まるで、牧羊犬に誘導されているかわいい羊たちのようです。
さあ、大興奮のビンゴ大会が始まります。

あっと言う間に半日が過ぎていきました。私たちのアウトドア・パーティーに会場を提供してくれた黒沢ハイランドのご厚意に心から感謝しつつのお開きとなりました。
みなさん、会場をきれいに片づけて帰りましょう。来年もまたここでアウトドア・パーティーやりたいですね。
Posted by Okuno at
10:16
│Comments(0)
2018年04月19日
パラダイム・シフト
ある日の、あるチームのトレーニング光景。
ピッチの周囲のジョギングから始まる。その間に、コーチはマーカーやコーンをセットする。ジョギングの後は体操、ストレッチ。コーンやマーカーを置いてステップ・ワーク。ここからボールを使ったトレーニングに入る。二人一組でのパス交換が終わると、グループでのパス&コントロールの練習。続いてシュートのパターン練習。ゴール・キーパーはいないことが多い。ここまででほぼ1時間経過している。後半は、ポゼッション・トレーニングとゲーム。最後に補強トレーニングが入ることもある。伝統的に、私たちのトレーニングはこのような構成だったように思う。私を含めて日本全国で、プレーヤーを経験してコーチになった者は、このように刷り込まれてきた。
今、私はサッカーのトレーニング(特に育成年代の)について、私自身の“パラダイム・シフト”が必要ではないかと強く感じている。私たちが刷り込まれてきた“要素分解・要素組立”方式から、サッカーの本質を再現しながらトレーニングをおこなう“要素複合”方式への転換である。そのためには、トレーニングの考え方の基盤になっている“パラダイム”を新たに書き換えなければいけない。“パラダイム”の転換なしに、トレーニング・メニューだけを工夫しても、なんとなくよく似たものにしかならない。
最近言われている“M-T-M”方式を取り入れても、例えば、試合で中盤の組み立てのパスをよくカットされて、カウンター攻撃を受けてしまう。トレーニングで次の試合までに改善したい。どうするか。パスが不正確だ⇒二人一組のインサイド・パスをもっと正確にできるように練習しよう。パスを受ける位置が悪い⇒ハンド・パスでサポートの位置を確認しよう。周囲の状況がつかめていない⇒パスを受ける前に周囲を見て、パス&コントロールの練習をしよう。4対2のポゼッションをしよう。OK。練習でできるようになったことを試合で生かそう。これが“要素分解・要素組立”方式である。しかし、トレーニングの成果が試合になかなか現れない。なぜなら、試合はトレーニング要素の足し算では構成されていないからだ。なぜ、私たちのトレーニングは、長い間このようであったのか。私には、野球のトレーニング方式が知らず知らず肌感覚として日本人に染みこんでしまっているのではないかと思われてならない。
例え話だが、太陽は東の空に上がって、西の海に沈んでいく。あるいは春夏秋冬、季節が巡る。日本人が見てもスペイン人が見てもそうだ。しかし、この現象を天動説で説明するのと、地動説で説明するのでは全く違ってくる。私たちは、試合での現象を見て、改善方法を考える時、いわば天動説から地動説への転換をしなくてはいけないのではないか。
サッカーの一流国に学ぶことは大切である。かつてはブラジルの個人技、ドイツの組織サッカー、最近ではスペインのトレーニング・メニュー。情報はあふれている。しかし、それを学ぶ私たちのパラダイムは以前のままだ。“パラダイム”の転換なしに、トレーニング・メニューを変更しても、なんとなくよく似たものにしかならない。チームを画期的にレベル・アップさせたいのなら、“要素分解・要素組立”というパラダイムから、サッカーの本質を再現しながらトレーニングをおこなう“要素複合”のパラダイムへの転換を急ごう。このことは、いずれ日本でも起こる。他に先駆けて取り入れることが他のチームとの違いを生み出す。
トレーニング・メニューに“サッカーの本質”を常に取り入れよう。サッカーの本質とは、目指すゴールがある、そのためにボールを奪い合う相手がいる、サポートしあう味方がいる、攻守の切り替えがある、シーンが常に変化しつつ連続する、プレーヤーに瞬時の判断が要求される、このようなことである。そのトレーニング・メニューには、これらの要素が組み込まれているか。要素還元トレーニングに試合のリアリティーがあるかどうかを考えるのは、“天動説”である。サッカーの本質が要求されているトレーニング・メニューの中で、要素の指導を行うのである。
プレーヤーは“やらされ感”を持っていないか。それを力で抑え込み、トレーニングに耐えることを強いるトレーニングでプレーヤーの資質は本当に引き出せるのか。トレーニングで一番大切なのは“ゾーン”に入っているかどうかだ。“ゾーン”に入ったら、どうなるか。心は熱く、頭は冷静に、課題に進んで取り組み、集中力を維持して全力でトレーニングに取り組んでいる。そうなっているかどうかは、プレーヤーの動きや目の輝きを見ればわかるはずだ。コーチはそれをサポートするためのコーチングを行い、それを途切れさせないように気を配る。
バレンシアCFオフィシャルアカデミー和歌山校では、サッカーのトレーニングについての自分のパラダイムを転換し、サッカーの本質を常に意識したトレーニングで、プレーヤーを“ゾーン”へ誘い込むことで、プレーヤーの資質を最大限引き出していくことに、私はチャレンジしていきたいと強く考えている。
ピッチの周囲のジョギングから始まる。その間に、コーチはマーカーやコーンをセットする。ジョギングの後は体操、ストレッチ。コーンやマーカーを置いてステップ・ワーク。ここからボールを使ったトレーニングに入る。二人一組でのパス交換が終わると、グループでのパス&コントロールの練習。続いてシュートのパターン練習。ゴール・キーパーはいないことが多い。ここまででほぼ1時間経過している。後半は、ポゼッション・トレーニングとゲーム。最後に補強トレーニングが入ることもある。伝統的に、私たちのトレーニングはこのような構成だったように思う。私を含めて日本全国で、プレーヤーを経験してコーチになった者は、このように刷り込まれてきた。
今、私はサッカーのトレーニング(特に育成年代の)について、私自身の“パラダイム・シフト”が必要ではないかと強く感じている。私たちが刷り込まれてきた“要素分解・要素組立”方式から、サッカーの本質を再現しながらトレーニングをおこなう“要素複合”方式への転換である。そのためには、トレーニングの考え方の基盤になっている“パラダイム”を新たに書き換えなければいけない。“パラダイム”の転換なしに、トレーニング・メニューだけを工夫しても、なんとなくよく似たものにしかならない。
最近言われている“M-T-M”方式を取り入れても、例えば、試合で中盤の組み立てのパスをよくカットされて、カウンター攻撃を受けてしまう。トレーニングで次の試合までに改善したい。どうするか。パスが不正確だ⇒二人一組のインサイド・パスをもっと正確にできるように練習しよう。パスを受ける位置が悪い⇒ハンド・パスでサポートの位置を確認しよう。周囲の状況がつかめていない⇒パスを受ける前に周囲を見て、パス&コントロールの練習をしよう。4対2のポゼッションをしよう。OK。練習でできるようになったことを試合で生かそう。これが“要素分解・要素組立”方式である。しかし、トレーニングの成果が試合になかなか現れない。なぜなら、試合はトレーニング要素の足し算では構成されていないからだ。なぜ、私たちのトレーニングは、長い間このようであったのか。私には、野球のトレーニング方式が知らず知らず肌感覚として日本人に染みこんでしまっているのではないかと思われてならない。
例え話だが、太陽は東の空に上がって、西の海に沈んでいく。あるいは春夏秋冬、季節が巡る。日本人が見てもスペイン人が見てもそうだ。しかし、この現象を天動説で説明するのと、地動説で説明するのでは全く違ってくる。私たちは、試合での現象を見て、改善方法を考える時、いわば天動説から地動説への転換をしなくてはいけないのではないか。
サッカーの一流国に学ぶことは大切である。かつてはブラジルの個人技、ドイツの組織サッカー、最近ではスペインのトレーニング・メニュー。情報はあふれている。しかし、それを学ぶ私たちのパラダイムは以前のままだ。“パラダイム”の転換なしに、トレーニング・メニューを変更しても、なんとなくよく似たものにしかならない。チームを画期的にレベル・アップさせたいのなら、“要素分解・要素組立”というパラダイムから、サッカーの本質を再現しながらトレーニングをおこなう“要素複合”のパラダイムへの転換を急ごう。このことは、いずれ日本でも起こる。他に先駆けて取り入れることが他のチームとの違いを生み出す。
トレーニング・メニューに“サッカーの本質”を常に取り入れよう。サッカーの本質とは、目指すゴールがある、そのためにボールを奪い合う相手がいる、サポートしあう味方がいる、攻守の切り替えがある、シーンが常に変化しつつ連続する、プレーヤーに瞬時の判断が要求される、このようなことである。そのトレーニング・メニューには、これらの要素が組み込まれているか。要素還元トレーニングに試合のリアリティーがあるかどうかを考えるのは、“天動説”である。サッカーの本質が要求されているトレーニング・メニューの中で、要素の指導を行うのである。
プレーヤーは“やらされ感”を持っていないか。それを力で抑え込み、トレーニングに耐えることを強いるトレーニングでプレーヤーの資質は本当に引き出せるのか。トレーニングで一番大切なのは“ゾーン”に入っているかどうかだ。“ゾーン”に入ったら、どうなるか。心は熱く、頭は冷静に、課題に進んで取り組み、集中力を維持して全力でトレーニングに取り組んでいる。そうなっているかどうかは、プレーヤーの動きや目の輝きを見ればわかるはずだ。コーチはそれをサポートするためのコーチングを行い、それを途切れさせないように気を配る。
バレンシアCFオフィシャルアカデミー和歌山校では、サッカーのトレーニングについての自分のパラダイムを転換し、サッカーの本質を常に意識したトレーニングで、プレーヤーを“ゾーン”へ誘い込むことで、プレーヤーの資質を最大限引き出していくことに、私はチャレンジしていきたいと強く考えている。
Posted by Okuno at
20:12
│Comments(0)
2018年03月21日
アカデミー体験会、大盛況! いよいよ開校へ!
3月19日(月)雨天のため、海南スポーツセンター体育館で実施しました。予想を上回るたくさんの子どもたちが参加してくれました。うれしかったです。
バレンシアジャパンから中谷さんも来てくださり、活気あふれる体験会になりました。

ウォーミングアップは、4人同時スタートのドリブル。他のプレーヤーにぶつからないようにコースを変えながら、しかも速くドリブルするためには、ボールだけを見ないで少し目線を上げる必要があります。集中力も身についていきます。
続いてステップワークとパスとコントロール・シュートのコンビネーション・トレーニング。集中して取り組まないと、次のプレーヤーに追い抜かれてしまいます。それでいて、パスは正確にコーンとコーンの間を通さなければなりません。さらに、次のポジションに速く移動するためには、いつも次のシーンを想定している必要があります。パターン練習ですが、次のシーンの予測は試合で絶対に必要な要素です。
三つ目のトレーニングは、ポゼッションです。激しいボールの奪いあい、ボールの受け方、攻める方向の意識、仲間へのコーチング、ボールがアウトになっても次々にコーチからボールが出されます。休憩している暇はありません。試合中の局面そのものです。
最後は、ライン上にサポート役を置いて、全員でゲーム。どちらのゴールを攻めても良いので、逆方向への展開は、相手チームの意表をついて効果的です。そのためには、ボールだけでなくフィールド全体を見渡せる視野の広さが要求されます。
体験会の最後に、バレンシアCFアカデミージャパンのゼネラルダイレクター・中谷さんから、「とても熱心に集中してトレーニングに参加してくれた。最初の一歩を踏み出すのは勇気がいることだけど、その一歩を踏み出した瞬間、既に進歩は始まっている。」とメッセージをいただきました。

参加してくれた子どもたちに感謝しています。この熱気をアカデミー和歌山校の開校につなげていきたいと強く思いました。
友だちと誘い合って、ぜひアカデミーに入会してください。バレンシアCFのエンブレムを誇らしく胸につけて、世界でも有数のクラブの一員として、いっしょにチャレンジしていきましょう!
アカデミー和歌山校開校案内
4月3日(火)海南スポーツセンター(雨天時:体育館)
17:00 受付開始
17:30~19:00 トレーニング
※中谷ダイレクターも来校予定です。
※U-9クラス、U-11クラスの合同で実施します。
入会希望、体験参加希望の方は、奥野修造(090-5242-0646)まで電話、ショートメールなどでご連絡ください。
開校準備の都合上、できれば3月31日(土)までにご連絡ください。
バレンシアジャパンから中谷さんも来てくださり、活気あふれる体験会になりました。

ウォーミングアップは、4人同時スタートのドリブル。他のプレーヤーにぶつからないようにコースを変えながら、しかも速くドリブルするためには、ボールだけを見ないで少し目線を上げる必要があります。集中力も身についていきます。
続いてステップワークとパスとコントロール・シュートのコンビネーション・トレーニング。集中して取り組まないと、次のプレーヤーに追い抜かれてしまいます。それでいて、パスは正確にコーンとコーンの間を通さなければなりません。さらに、次のポジションに速く移動するためには、いつも次のシーンを想定している必要があります。パターン練習ですが、次のシーンの予測は試合で絶対に必要な要素です。
三つ目のトレーニングは、ポゼッションです。激しいボールの奪いあい、ボールの受け方、攻める方向の意識、仲間へのコーチング、ボールがアウトになっても次々にコーチからボールが出されます。休憩している暇はありません。試合中の局面そのものです。
最後は、ライン上にサポート役を置いて、全員でゲーム。どちらのゴールを攻めても良いので、逆方向への展開は、相手チームの意表をついて効果的です。そのためには、ボールだけでなくフィールド全体を見渡せる視野の広さが要求されます。
体験会の最後に、バレンシアCFアカデミージャパンのゼネラルダイレクター・中谷さんから、「とても熱心に集中してトレーニングに参加してくれた。最初の一歩を踏み出すのは勇気がいることだけど、その一歩を踏み出した瞬間、既に進歩は始まっている。」とメッセージをいただきました。

参加してくれた子どもたちに感謝しています。この熱気をアカデミー和歌山校の開校につなげていきたいと強く思いました。
友だちと誘い合って、ぜひアカデミーに入会してください。バレンシアCFのエンブレムを誇らしく胸につけて、世界でも有数のクラブの一員として、いっしょにチャレンジしていきましょう!
アカデミー和歌山校開校案内
4月3日(火)海南スポーツセンター(雨天時:体育館)
17:00 受付開始
17:30~19:00 トレーニング
※中谷ダイレクターも来校予定です。
※U-9クラス、U-11クラスの合同で実施します。
入会希望、体験参加希望の方は、奥野修造(090-5242-0646)まで電話、ショートメールなどでご連絡ください。
開校準備の都合上、できれば3月31日(土)までにご連絡ください。
Posted by Okuno at
20:48
│Comments(0)
2018年03月17日
バレンシアCFオフィシャルアカデミー和歌山校 開校します!
いよいよアカデミー体験会が近づいてきました。
例えるなら、新規オープンするパン屋さんの気分です。パン作りの修業は十分積んできた。一度食べてもらえば、お客さんに喜んでもらえる自信はある。しかし、お客さんは本当に来てくれるだろうか? そんな気分です。
そもそもなぜ和歌山校をやりたいと思ったのか。
スペイン・サッカーの魅力を和歌山の子どもたちにも知ってもらいたい、強烈にそう思ったからです。トレーニングの方法だけでなく、ホームゲームを迎えた時のメスタージャ・スタジアムの周囲の雰囲気、町中にサッカー場が点在する風景、草サッカーと呼んでも問題ないと思われる試合に熱中しているプレーヤーの、そして応援している人々の熱気、そんなものを知ったら、もっともっとサッカーが好きになってくれるはずだ。私がそうであったように。
私が海外のサッカーに惹かれるようになったきっかけは、高校生の時のサッカー部の顧問の先生が8ミリフィルムで見せてくれた、マンチェスターユナイテッドのチャンピオンズカップの決勝戦のジョージ・ベストのかっこいい姿でした。
大学生になり、初めてのヨーロッパ旅行で、イングランド2部リーグの試合を観戦し、ドイツではバイエルン・ミュンヘン対シャルケ04の試合で、ベッケンバウアーやゲルト・ミュラーのプレーを見ました。40年経った今でも覚えています。
1982年のスペイン・ワールドカップでは西ドイツ対フランスの準決勝戦や決勝戦も観戦しました。
今から10数年前、中谷さんと知り合いました。中谷さんが私の弟の大学サッカー部の後輩であったという縁で、「スペイン・サッカー教室」と銘打って中谷さんと、中谷さんが連れてこられたスペイン人コーチに講習会をしてもらいました。最初は、どんなメニューで練習するのだろうということが興味の中心でした。それ以来、ずっと毎年「スペイン・サッカー教室」を開催してもらっている内に、練習メニューではないところに、その指導法の神髄があると感じるようになりました。練習の強度や、テンポや、声掛けのタイミングなどのマニュアル化しにくいところにこそ、指導力がにじみ出るのだと考えるようになりました。
そして、現地を訪問したい、トップ・レベルのスペインのサッカーではなく、私たちと同じレベルのクラブや子供たちはどんなふうにサッカーに取り組んでいるのだろうか、何があの世界でもトップ・クラスのサッカーの基盤になっているのだろうか、ぜひ知りたいと思い、退職した年に、結果的には17日間と短い期間でしたが、中谷さんのお世話になってバレンシアを訪問しました。スペイン人のお宅にホームステイさせていただき、スペイン語学校に通い、地元クラブの練習や試合を見せてもらい、中谷さんのお世話で留学している中学生の話を聞き、リーガの試合やチャンピオンズ・リーグを観戦するなど、濃密な時間を過ごすことができました。
そして、スペイン・サッカーの魅力を和歌山の子どもたちにも知ってもらいたい、強烈にそう思い始めたのです。
「夢・熱・仲間」。私が教員だった時、卒業していく生徒たちに送った言葉です。いつも何かに夢を持って、それに向かっていく情熱を持ち続け、仲間とともに歩んでいく。私自身も、ずっとこれからもそうありたいと思います。
「バレンシアCFオフィシャルアカデミー和歌山校」は、そんな夢の一つの形でありたいと願っています。
例えるなら、新規オープンするパン屋さんの気分です。パン作りの修業は十分積んできた。一度食べてもらえば、お客さんに喜んでもらえる自信はある。しかし、お客さんは本当に来てくれるだろうか? そんな気分です。
そもそもなぜ和歌山校をやりたいと思ったのか。
スペイン・サッカーの魅力を和歌山の子どもたちにも知ってもらいたい、強烈にそう思ったからです。トレーニングの方法だけでなく、ホームゲームを迎えた時のメスタージャ・スタジアムの周囲の雰囲気、町中にサッカー場が点在する風景、草サッカーと呼んでも問題ないと思われる試合に熱中しているプレーヤーの、そして応援している人々の熱気、そんなものを知ったら、もっともっとサッカーが好きになってくれるはずだ。私がそうであったように。
私が海外のサッカーに惹かれるようになったきっかけは、高校生の時のサッカー部の顧問の先生が8ミリフィルムで見せてくれた、マンチェスターユナイテッドのチャンピオンズカップの決勝戦のジョージ・ベストのかっこいい姿でした。
大学生になり、初めてのヨーロッパ旅行で、イングランド2部リーグの試合を観戦し、ドイツではバイエルン・ミュンヘン対シャルケ04の試合で、ベッケンバウアーやゲルト・ミュラーのプレーを見ました。40年経った今でも覚えています。
1982年のスペイン・ワールドカップでは西ドイツ対フランスの準決勝戦や決勝戦も観戦しました。
今から10数年前、中谷さんと知り合いました。中谷さんが私の弟の大学サッカー部の後輩であったという縁で、「スペイン・サッカー教室」と銘打って中谷さんと、中谷さんが連れてこられたスペイン人コーチに講習会をしてもらいました。最初は、どんなメニューで練習するのだろうということが興味の中心でした。それ以来、ずっと毎年「スペイン・サッカー教室」を開催してもらっている内に、練習メニューではないところに、その指導法の神髄があると感じるようになりました。練習の強度や、テンポや、声掛けのタイミングなどのマニュアル化しにくいところにこそ、指導力がにじみ出るのだと考えるようになりました。
そして、現地を訪問したい、トップ・レベルのスペインのサッカーではなく、私たちと同じレベルのクラブや子供たちはどんなふうにサッカーに取り組んでいるのだろうか、何があの世界でもトップ・クラスのサッカーの基盤になっているのだろうか、ぜひ知りたいと思い、退職した年に、結果的には17日間と短い期間でしたが、中谷さんのお世話になってバレンシアを訪問しました。スペイン人のお宅にホームステイさせていただき、スペイン語学校に通い、地元クラブの練習や試合を見せてもらい、中谷さんのお世話で留学している中学生の話を聞き、リーガの試合やチャンピオンズ・リーグを観戦するなど、濃密な時間を過ごすことができました。
そして、スペイン・サッカーの魅力を和歌山の子どもたちにも知ってもらいたい、強烈にそう思い始めたのです。
「夢・熱・仲間」。私が教員だった時、卒業していく生徒たちに送った言葉です。いつも何かに夢を持って、それに向かっていく情熱を持ち続け、仲間とともに歩んでいく。私自身も、ずっとこれからもそうありたいと思います。
「バレンシアCFオフィシャルアカデミー和歌山校」は、そんな夢の一つの形でありたいと願っています。
Posted by Okuno at
12:18
│Comments(0)